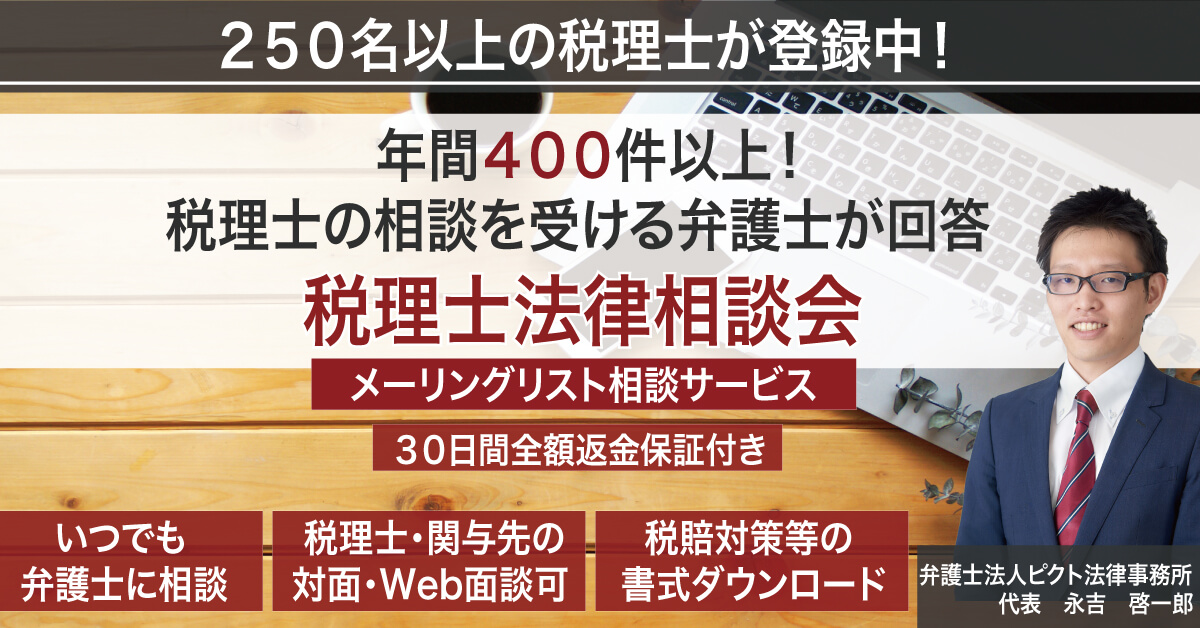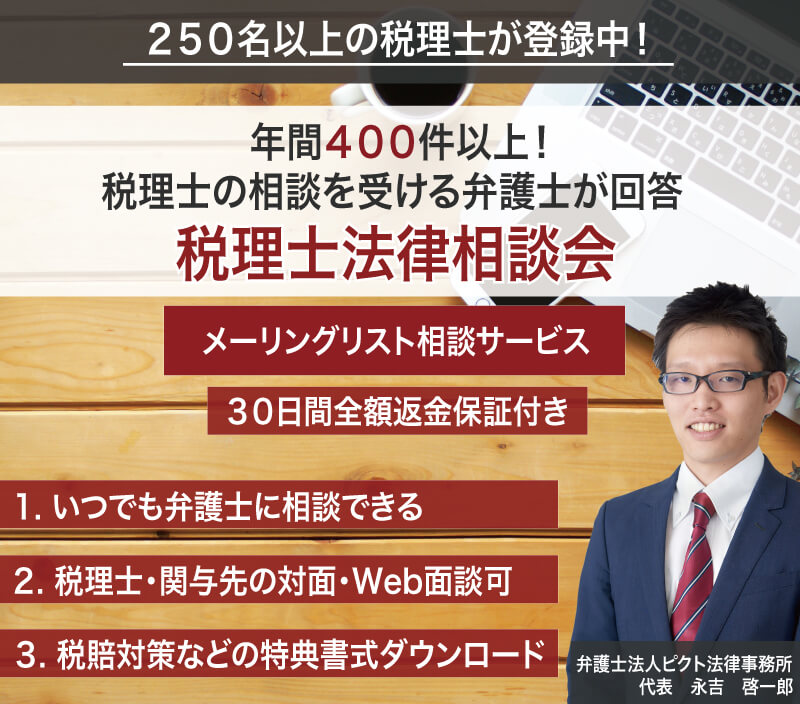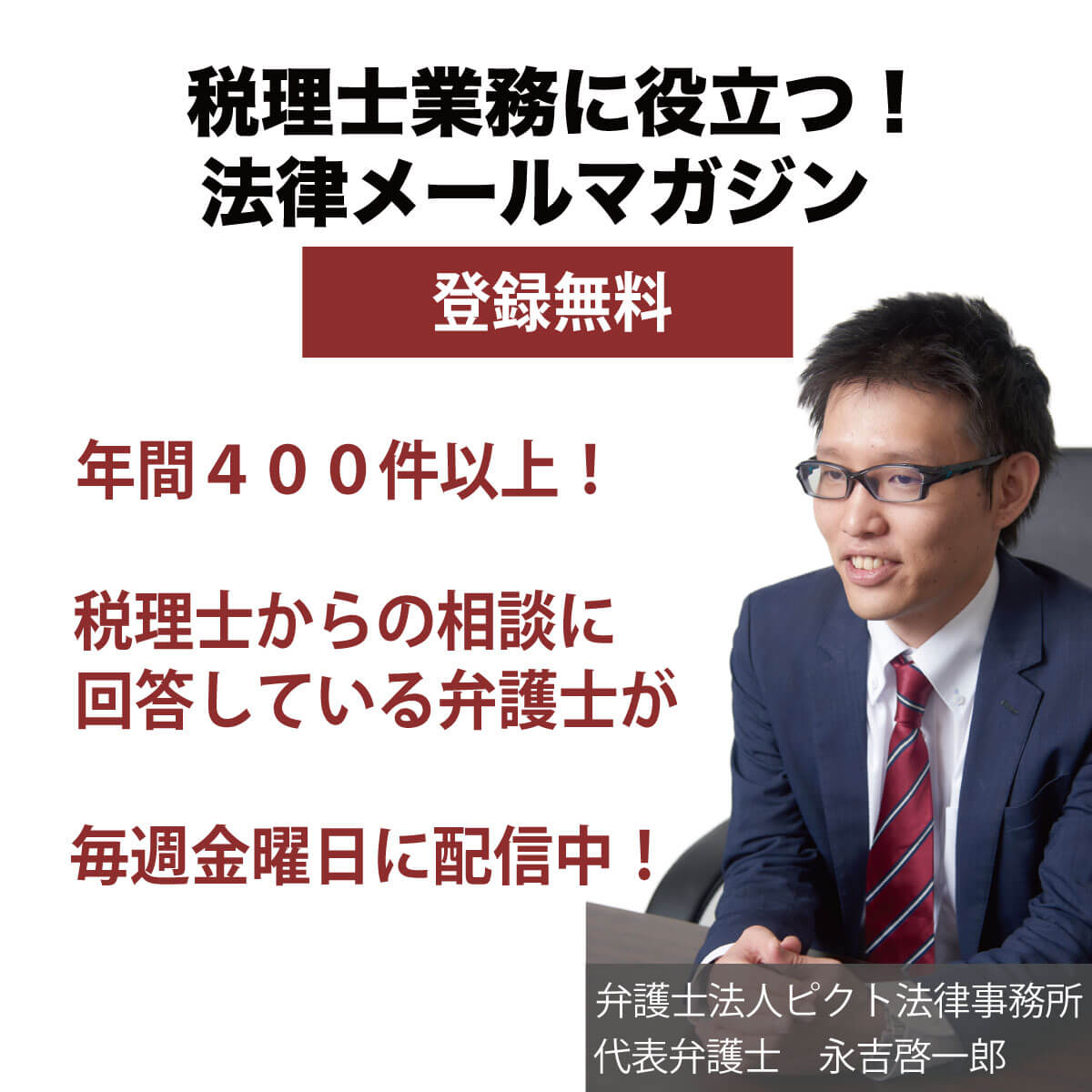遺言の撤回・変更のルール〜遺言の法務と税務⑦〜
前回、遺言の効力内容を確定するためには、作成された遺言をどのように解釈するのかがポイントになるという記事を書きました。これにも関連するのですが、遺言書作成後、効力発生前(つまり、遺言者の死亡前)に、その遺言の内容を変更したり、撤回されたりということが、しばしあります。もちろん、遺言の内容が変わったり、撤回されていたりすれば、相続税申告の内容は大きく変わってしまいます。
今回は、遺言の変更や撤回のルールについて、解説いたします。
【目次】
1 遺言の撤回や変更のルール
遺言は、遺言者の死亡まで効力が発生しないことから、その最終意思を尊重するために遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回したり、変更したりすることができます。
以下では、具体的にこの遺言の方法にどのように遺言の撤回や変更(撤回と追加)をするのかという点を見ていきたいと思います。
- ◯遺言による撤回や変更(民法1022条)
- ◯抵触行為による撤回(民法1023条)
- ◯破棄による撤回(民法1024条)
の3つがあります。
2 遺言による撤回や変更(民法1022条)
まず、遺言者は、いつでも「遺言の方式」に従って撤回・変更(撤回と追加)することができます(民法1022条)。
遺言による撤回・変更の場合、もともとの遺言書と同一の方式である必要はありません。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言により撤回・変更することは法律上可能です。なお、【「遺言の方式」に関してはこちらの記事】をご覧ください。
ただし、自筆証書は後に紛争になることが多いものです。特に元々公正証書遺言があって、それを自筆遺言で撤回・変更するということになると、相続人間で揉め事が起こる可能性はかなり高くなります。ですので、実務上は、公正証書遺言によるべきです。
(遺言の撤回)
民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
3 抵触行為による撤回(民法1023条)
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法は、以下の場合には、遺言は撤回されたものとみなされるとしています。
- ①前の遺言と後の遺言内容が抵触する場合(第1項)
- ②遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合(第2項)
わかりやすい例を挙げると
です。
この場合、前の遺言を撤回しなけれは、後の遺言や生前処分の内容を実現できないという関係(抵触)にありますので、前の遺言の「甲土地をBに与える」という部分が、撤回されたものと扱われます。このようなわかりやすい事例は良いとして、民法上、この「抵触」に当たるか否かについて、紛争になるケースがままあります。
大審院(昔の最高裁)昭和18年3月19日の古い判例になりますが、この「抵触」の意味は、思ったよりも緩やかに判断されており、この判例が現在も一応の判断基準?となっているので、注意が必要です。原文を掲載しようかと思いましたが、旧字体ですので、かなり読みにくい(PCで書くのも難しいです)ので、要点をまとめますと以下のように言っています。
例えば、
これは、遺贈の対象となっている不動産の遺贈と協議離婚は、客観的には矛盾するものではないですが、「両立させない趣旨のもとになされた」として、撤回となりました。
そして、実務上さらに難しい問題は、撤回の有無と撤回の範囲を確定することです。
撤回の有無もさることながら、撤回の範囲については、最終的に遺言者の意思解釈の問題になってしまいます。そして、この撤回の範囲により、遺言の効力が変わってしまいます。
このあたりについては、実際に税理士の先生からいただいた相談事例を前提に、次回遺言シリーズの総仕上げとして、また取り上げたいと思います。
4 破棄による撤回(民法1024条)
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言者が遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合、破棄した部分について、遺言は撤回されたものとみなされます。
なお、当然ですが、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されているので、遺言者が遺言を破棄しても撤回になりません。撤回する場合は新たに遺言書を作成するということになります。
5 その他、遺言の復活・撤回権の放棄など
その他の遺言の撤回・変更のルールについても、簡単に見てみましょう。
5.1 遺言の非復活主義
(撤回された遺言の効力)
民法第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
まず、一度、撤回がなされるとその後、撤回行為のさらなる撤回などにより効力が生じなくなったとしても、最初に撤回された遺言の効力は復活しないと定めています。
例えば、
ただし、第1遺言の撤回が詐欺または脅迫を理由に取り消された場合には、効力が復活する旨規定しています(民法1025条但書)。この場合には、撤回行為が遺言者の真意に出たものでないことが明らかなためそのようにされています。
5.2 遺言の撤回権の放棄
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
遺言者は、遺言の撤回権を放棄できないとされています。これは、遺言者の最終意思を尊重するという遺言制度の趣旨からして当然でしょう。例えば、相続人や受遺者と撤回しない旨を合意をしようが、遺言書に撤回をしない旨を記載しようが、拘束されず、撤回することができます。
6 まとめ
以上が、遺言の撤回、変更についてのルールになります。いろいろな方法がありますが、つまるところ、遺言者が元気なうちは、公正証書遺言によることを強くお勧めします。
「抵触行為」があったか否かやその範囲により、遺言の効力にも影響を及ぼしてしまいますので、遺言者さんが亡くなった後に、親族間で争いになってしまうことも多いです。公正証書を作り直すのは、遺言者さんにとって面倒なことであるのですが、残された親族の争いを防ぐため明確な遺言書を作りなおしましょう。
さて、長期間にわたっている遺言シリーズですが、次回を一旦、最終回としたいと思います。最終回では、この記事でも取り上げた遺言の撤回の話を含む税理士さんから実際のご相談いただいた事例を前提ととして、総合事例検討としたいと思います。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日