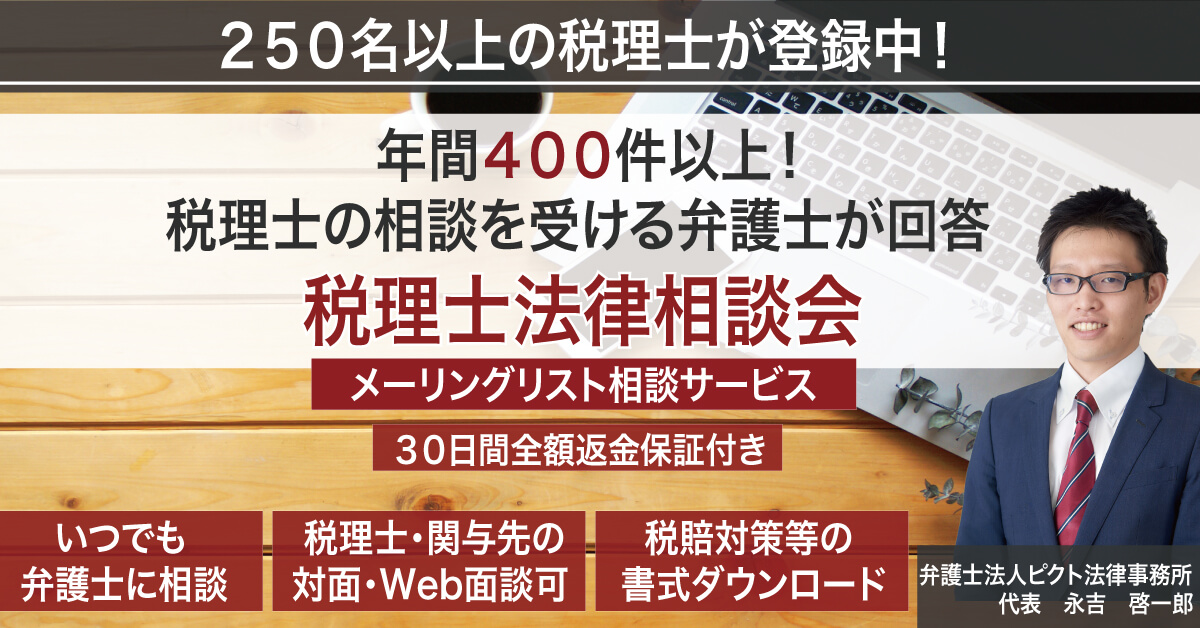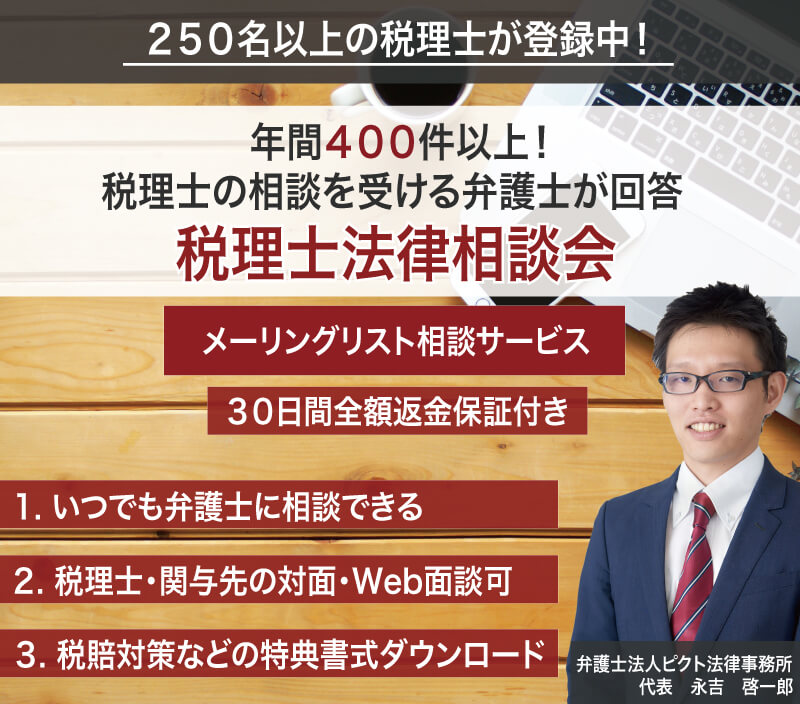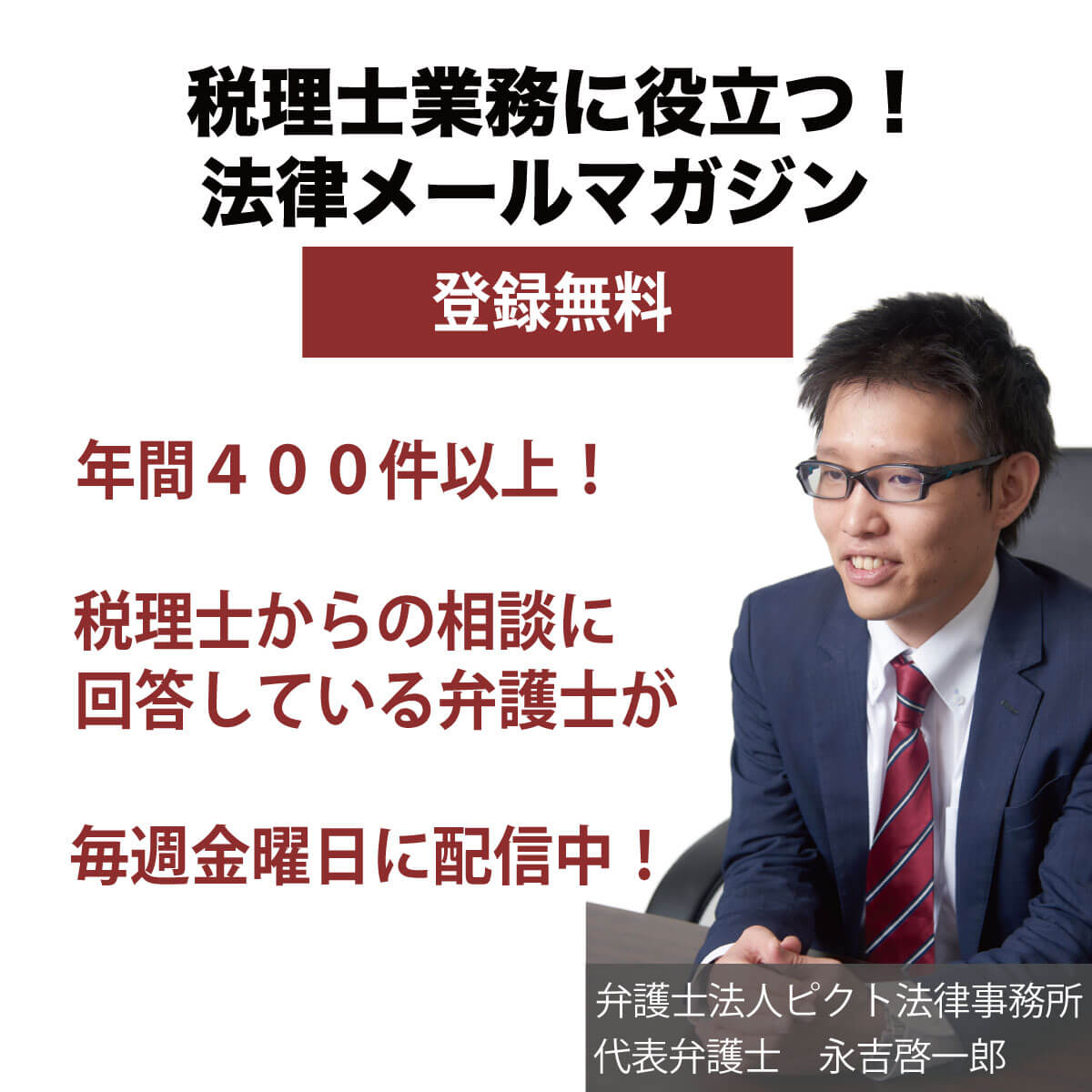限定承認における税務上の注意点
前回は、民法による限定承認の効果・方法と注意点について解説しました。今回は、限定承認をした場合についての税務上の注意点について解説したいと思います。税理士の先生は是非、ご参考になさってください。
【目次】
1 譲渡所得課税
通常の単純承認による相続の場合と異なり、限定承認の場合、被相続人(死んだ人)から相続人への譲渡所得課税が生じます。
1.1 みなし譲渡所得課税
まず、限定承認をする場合の特別な規定としては、みなし譲渡所得課税(所得税法59条1項1号)があります。
税理士の先生に説明するのも、釈迦に説法感が否めませんが、譲渡所得課税の趣旨は,資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタルゲイン)を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に,これを清算して課税するものである。
確かに、相続時でも被相続人(死んだ人)から相続人に対して資産の移転はあるのですが、通常の相続(単純相続の場合)は譲渡所得において担税力を見出し難い無償譲渡であることから、課税繰延べ(取得費の引き継ぎ)ということにされています(所得税法60条1項)。
しかし、限定承認の場合には、相続時に、その時点の直で被相続人(死んだ人)が譲渡したものとみなして、被相続人に対して、譲渡所得課税されます(所得税法59条1項1号)。これは、前回の限定承認の法務的な記事でも書いた通り、限定承認制度の趣旨は、被相続人の債務として清算するという点にあるからです。つまり、この課税により、被相続人の資産を保有していた期間のキャピタルゲインへの課税を終了させ、限定承認の清算手続きの中で、所得税も債務として扱われ、相続財産を超える部分は切り捨てられるということになります。
また、相続後に相続人がその資産を譲渡する場合には、取得費を相続時の時価とします(所得税法60条2項)ので、課税の重複が起こらないような設計になっています。
1.2 みなし譲渡所得課税の注意点
みなし譲渡所得課税が生じた場合、その法的構成より、下記の特別控除の適用が認められませんので、ご注意下さい。
1.2.1 居住用資産の譲渡の特別控除(租税特別措置法35条)
居住用資産の譲渡については、3000万円の特別控除の適用があります。しかし、限定承認の場合、相続時に被相続人から相続人に譲渡があったものとみなされます。ですので、相続人が生計を別にする兄弟姉妹である場合を除き、譲渡当事者が「当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの」(租税特別措置法35条2項1号括弧書き、租税特別措置法施行令23条2項・20条の3の1項各号)にあたってしまいその適用が受けられませんので注意が必要です。
1.2.2 居住用資産の譲渡所得の軽減税率(租税特別措置法31条の3)
居住用資産の譲渡所得については、軽減税率の適用があります。しかし、限定承認の場合には、特別控除と同様の理由で、相続人が生計を別にする兄弟姉妹である場合を除き、譲渡当事者が「当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの」(租税特別措置法31条の3弧書き、租税特別措置法施行令20条の3の1項各号)にあたってしまいその適用が受けられません。
2 限定承認と準確定申告の期限
限定承認の熟慮期間と準確定申告の期限についての詳細はこちらの記事をご参照いただきたいのですが、前者は、相続の開始を相続人が知ってから3か月、後者は4か月以内となります。
多くの場合、限定承認を選択するかについては、債務超過か否かがポイントとなるところ、相続財産の調査を熟慮期間内にすることは困難ですので、熟慮期間を延長することをお勧めしています。
しかし、限定承認の熟慮期間を延長したからといって、準確定申告期限まで延長される効果はありません(東京高裁平成15年3月10日)。ですので、熟慮期間を延長しても、熟慮期間中に準確定申告期限が来てしまうという事態になりえます。
この点は、とても難しい問題を含んでいて、解説書等では、限定承認の申述前においても、準確定申告の内容を反映した準確定申告をすべきであるという説明も多されますが、この準確定申告行為自体は、被相続人(死んだ人)の租税債務の確定行為にあたりえますので、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)に該当し、法定単純承認となり、その後の限定承認は認められないのではないかという問題があります(法定単純承認についてはこちらの記事)。法定単純承認にあたってしまうとすれば、限定承認をする場合で、熟慮期間を延長する場合は、無申告のままの状態とすることになると考えられます。そして、その場合、延滞税納税義務が生じるというのが裁判例(東京高裁平成15年3月10日)の考え方になります。延滞税は、そのほかの事情にかかわらず、納期限の経過により生じるというのが理由です。
現状の制度を、前提にするならば、せめて延滞税の免除の規定(国税通則法63条6項4号)の柔軟な運用や無申告加算税の「正当な理由」(国税通則法66条1項但書)の運用で、柔軟に対応していただければと思いますし、立法政策としても検討してもらいたい部分です。
税理士の先生としては、この点についても、お客様にご説明の上、どのような対策を講じるのか決定していただければと思います。
3 租税債権に対する弁済
税務判断についての話ではありませんが、限定承認をする場合に租税債権をどのように扱うかも見ておきましょう。
3.1 公告期間満了前の弁済拒絶
公告期間満了前の弁済拒絶の詳細についてはこちらの記事をご参照いただきたいのですが、公告期間満了前は、限定承認をした者は、租税債権についても弁済拒絶をするうことが可能です。
確かに、租税債権は、国税徴収法8条の国税債権優先の原則により、一般債権に優先するものです。ただし、優先する債権の中でも、優劣を確定する必要があるため、公告期間満了前は、弁済拒絶が可能であると考えられます。
3.2 公告期間満了後の弁済の順位
公告期間満了後の弁済の順位の詳細については、こちらの記事をご参照いただきたいのですが、上述の通り、限定承認の場合には、みなし譲渡所得課税が発生し、相続時に被相続人(死んだ人)から相続人に対して、資産を譲渡したものとみなされます。そして、この譲渡所得にかかる租税債権についても、国税徴収法8条の国税債権優先の原則が適用されます。ですので、限定承認に関しては、相続開始前から生じている被相続人の債務を弁済するよりも、このみなし譲渡所得課税を含めた、準確定申告により確定した所得税を先に弁済するということになります。
4 まとめ
以上、限定承認をする際に注意したい税務上の問題を解説しました。税理士の先生のご参考になれば嬉しいです。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日