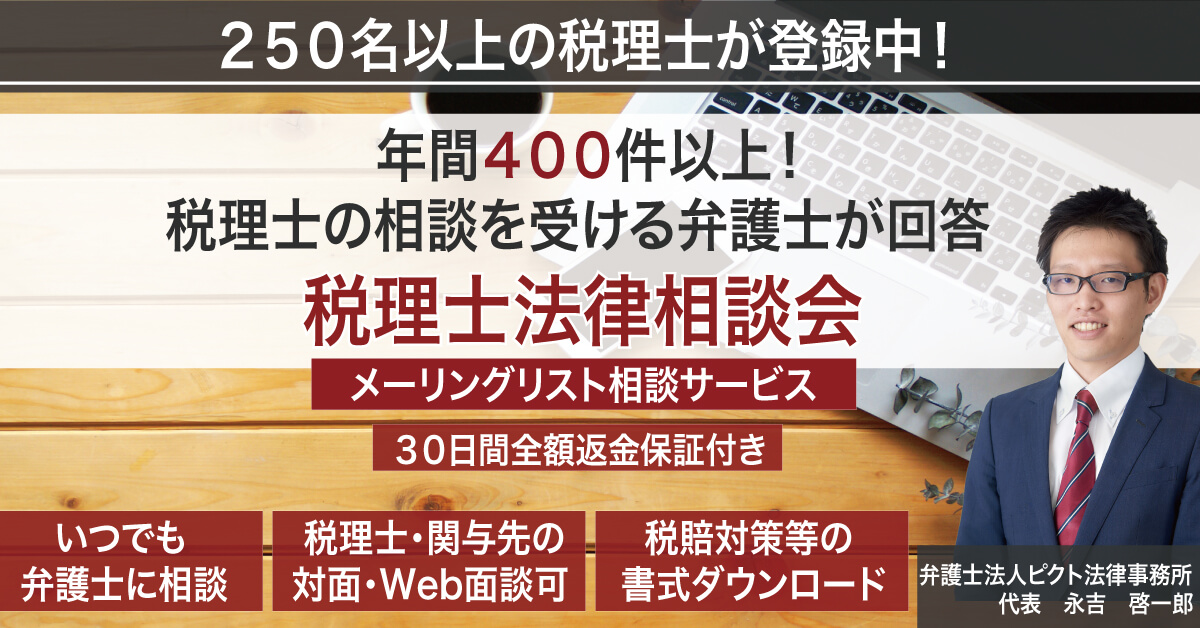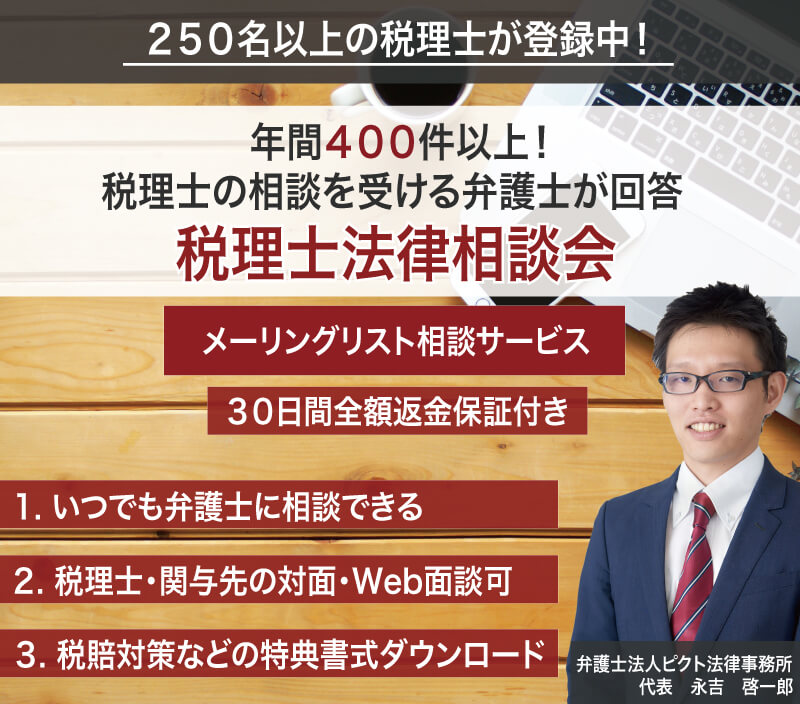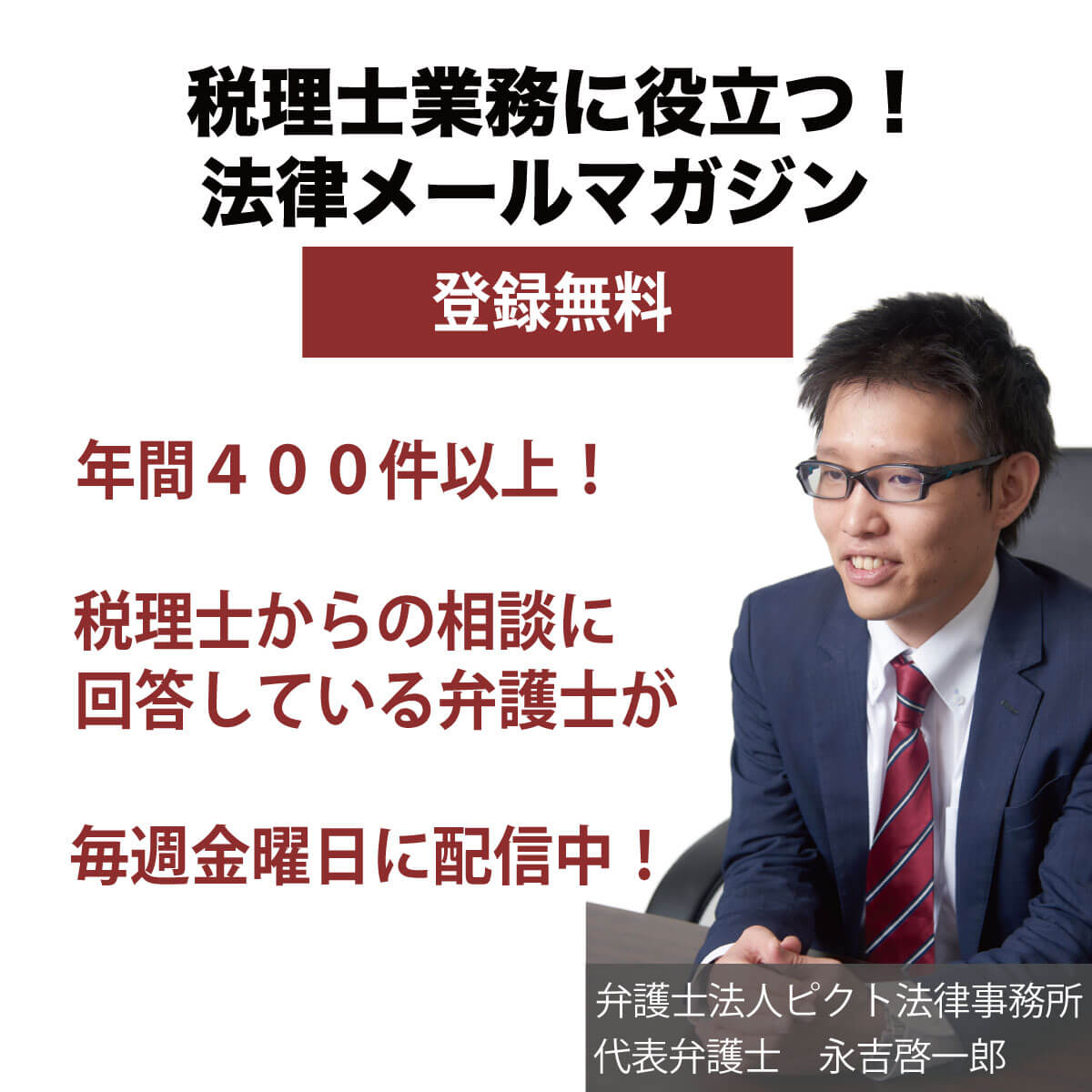相続人が不明・不存在の場合における相続財産の法律関係
当サイトでは、税理士の先生が知っておくべき相続(主に民法)について解説をしてきました。今回は、相続が発生したのですが、相続人が不明または不存在の場合に、法的に相続財産はどのように扱われるのかという点について、解説したいと思います。
【目次】
1 相続財産法人化と相続財産管理人
(相続財産法人の成立)
民法第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
いきなり民法の条文から失礼します。この条文からわかる通り、相続人が不明または不存在である場合には、積極財産と消極財産を含め相続財産は法人となります。
1.1 法人化される趣旨
本来、民法上、帰属する者がいない財産については、不動産は国庫に、動産は占有者に帰属すると定められています(民法239条)。そうすると、被相続人(死んだ人)の債権者などは、その財産に対して、債権回収ができないという事態になりかねません。また、相続人が後から現れた場合にも、法律関係が複雑になってしまいます。
そこで、民法は相続財産について、相続人が不明または不存在の場合には、法人を成立させ、後述の相続財産の管理人を選任して、その法人の代理権を与えることで、相続人を探させたり、相続財産の管理をさせ、清算手続きまで行わせることにしました(民法952条)。
このようにすれば、相続財産の清算手続きの中で、相続財産である不動産を売却して、その対価から債権者に債務の弁済をすることも可能になります。
1.2 法人化される要件
相続財産が法人化される要件ですが、上記の条文からも明らかな通り、
ということになります。具体的には、
◯相続放棄(民法938条)、相続人の欠格(民法891条)または推定相続人の排除(民法892条)により、相続人が存在しなくなった場合
が考えられます。
なお、上記の要件があっても、相続財産の全てについて包括遺贈がされた場合には、「包括受遺者(全ての財産の遺贈を受けた者)は、相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)ことになりますので、「相続人があることが明らかでないとき」には当たりません。
また、戸籍上の相続人となる者が行方不明や生存不明のというのみでは、要件は満たされません。この場合、不在者の財産管理についての規定(民法25条以下)、失踪宣告の規定(民法30条以下)等の適用の問題になります。
1.3 相続財産の管理人の選定
上記の要件である「相続人があることが明らかでないとき」に該当すれば、相続財産は当然に法人となります。ただし、法人となったとしても、その事務処理を行う者が必要です。そこで、民法は、そのような場合に、相続財産法人を代理する者を選任するという手続きを用意しています。
(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 ・・・省略・・・
家庭裁判所が、「利害関係人又は検察官の請求」により、相続財産管理人を選任することになりますが、この「利害関係人」とは、被相続人の債権者、債務者や特定遺贈を受けた者等が当たります。いずれも、相続財産の管理・清算に利害関係を有する者だからです。例えば、債権者であれば、相続財産から債権の回収をする権利がありますよね。
また、詳細は、後述しますが「特別縁故者」として、相続財産の分与請求をしようとする者も含まれます。
なお、このうち、特定遺贈を受けた者については、仮に遺言について遺言執行者が定められている場合には、その遺贈を実現するためには遺言執行者がいれば可能ですので、相続財産管理人の選任は不要と実務上はされています。
1.4 相続財産管理人の職務権限
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(・・・省略・・・)について準用する。
条文上はこのようにされていますが、内容を説明すると、相続財産管理人は、
②家庭裁判所の命令により、相続財産の保存に必要とされる財産の処分
③相続財産の保存行為と物または権利の性質を変えない範囲において、その利用又は改良を目的とする行為
◯家庭裁判所の許可を得た上での
④物または権利の性質を変えることになる財産の利用や改良行為
⑤相続財産の換価のための競売手続きや任意売却等の財産の処分
を行います。
具体的には、相続財産目録を作成した上で、相続財産を管理し(賃料収入等があれば受領等)、必要があれば相続財産(建物等)を修理したりします。また、債権の回収や時効の中断措置等の債権の実現行為等も行います。
さらに、相続債務がある場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、相続財産(不動産等)を競売や任意売却により換価して、債務の弁済等を行います。
2 3つの公告と法律関係
相続財産が法人化され、相続財産管理人が選任されると清算に向けた手続きが開始するのですが、最終的な清算までには、以下の3つの公告手続きがなされます。この3つの公告手続きを基準に相続財産法人の法律関係を見ていくのが実務上は有用かと思いますので、その視点で解説します。
2.1 ①相続財産管理人が選任されたことの公告
民法第952条 ・・・省略・・・
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
とされており、相続財産管理人が選任されれば、家庭裁判所が、公告をします。
そして、2か月以内に相続人が現れなければ、相続財産管理人が②の公告を行い清算手続きに着手していきます(根拠は下記の民法957条1項参照)。
2.2 ②相続債権者や受遺者に対する公告(民法957条)
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
①の公告から2か月を経過すると、相続財産管理人が相続債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定めて、請求の申出をするように公告することになります。
そして、債権者及び受遺者への財産の弁済がなされていきます。この際の弁済順位等のルールは、民法957条2項が、限定承認の規定を準用しておりますので、そのルールに基づくことになります。準用される限定承認の規定はこちらの記事をご覧ください。
なお、こちらの記事の第4順位を見ていただければと思いますが、この債権申出期間内に申し出をしなかった債権者等も弁済を受ける場合が想定されていますので、こちらの期間が経過したからといって、債権者等は、自己の債権を一切主張することができなくなるわけではありません。
2.3 ③相続人の捜索の公告
(相続人の捜索の公告)
民法第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
②の公告期間満了後、それでも相続人が現れない場合には、相続人がいるならば権利を主張するようにさらに公告します。
この公告は、後述の特別縁故者・国庫帰属の制度を維持するための公告になります。あとから相続人が現れたとしても、特別縁故者・国庫帰属に影響はありません。
そして、民法958条の2により、この公告の期間の経過をもって、相続債権者や受遺者は、権利主張できなくなります。
つまり、この3つ目の公告期間の満了をもって、相続人、相続債権者及び受遺者は失権します。
(権利を主張する者がない場合)
民法第958条の2 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
3 最終的な財産の帰趨
「2」の手続きを行うと、③の公告期間満了時に相続人、相続債権者及び受遺者は失権することになります。もちろん、「2」の手続で、相続財産の清算手続きはされていますが、その清算手続きしても、なおも余った相続財産(以下、「残余財産」といいます。)はどのようになるのでしょうか。
3.1 特別縁故者制度と国庫への帰属
相続財産法人の清算後の残余財産については、特別縁故者への相続財産の分与(民法958条の3)と国庫への帰属(959条)についての2つの規定があります。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
となっています。つまり、清算手続終了後の残余財産については、特別縁故者に対する財産分与があればその特別縁故者に、それ以外の場合は国庫へ帰属することになります。
そして、特別縁故者制度については詳細を別記事で解説しますが、この制度は、残余財産を国庫に帰属させるよりも、被相続人(死んだ人)の生前に特別な関係があったものに財産を与える方が被相続人の意思に沿っていると判断される者に家庭裁判所の裁量で、財産を与えるものになります。
税理士の先生からご質問をいただくことがあるのですが、債務等の消極財産は含まれません。あくまでも、所有者がいなくなった財産をどうするかという「積極財産」を分与する制度です。③の公告期間満了で、失権していることからも明らかですね。
3.2 「2」の手続きの途中で相続人が現れた場合
これまでの記述で、明らかになっていますが、この場合について税理士の先生からご質問をいただくことも多いので、この点も改めて解説します。
まず、上記③の公告期間が満了するまでに、相続人が現れた場合には、相続財産法人は、その成立の時に遡って、なかったものとされます。つまりは、最初から相続財産法人は存在しなかったものとして扱われるのです。
(相続財産法人の不成立)
第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
しかし、上述のように相続財産管理人は、相続財産(例えば「不動産」)を処分・換価して、債権者に債務の弁済をしたりします。このような財産の処分(例えば「不動産の譲渡」)があった後に相続人が現れた場合、そもそも法人がないことになり、財産処分が無効等になってしまうと誰も相続財産管理人がする売却には応じなくなってしまいますよね。もちろん、弁済を受けた債権者も後から弁済は無効だと言われても困ります。
そこで、仮に財産処分や弁済のあとに相続人が現れたとしても、その行為が相続財産管理人の権限内の行為である場合は、財産の処分や弁済の効力は否定されないということにしています。これが、上記の民法955条但書の意味です。
なお、上記③の公告期間満了後には、相続人は失権していますので、相続人が現れたとしても、相続財産法人の成立は否定されません。
4 まとめ
以上が、相続人が不明・不存在の場合における相続財産の法律関係になります。相続財産が法人となりその後どのような流れで財産が清算されていくのかについての法律についての記事を書きました。
次回は、この記事を前提に相続財産法人が成立した場合の税務上の注意点を解説したいと思います。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日