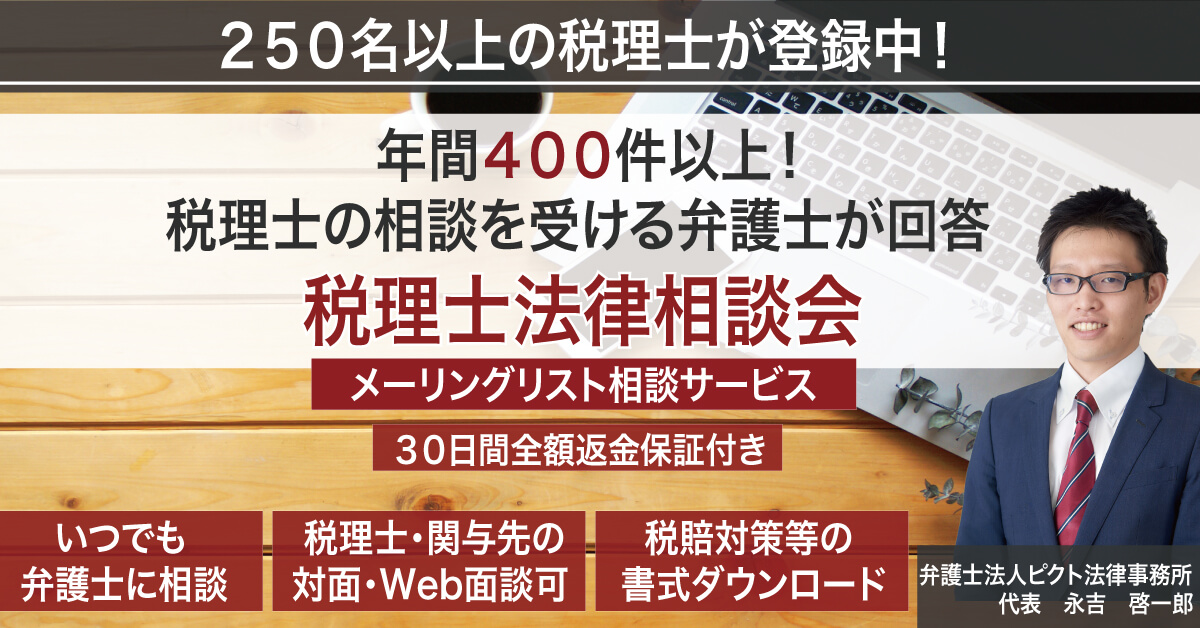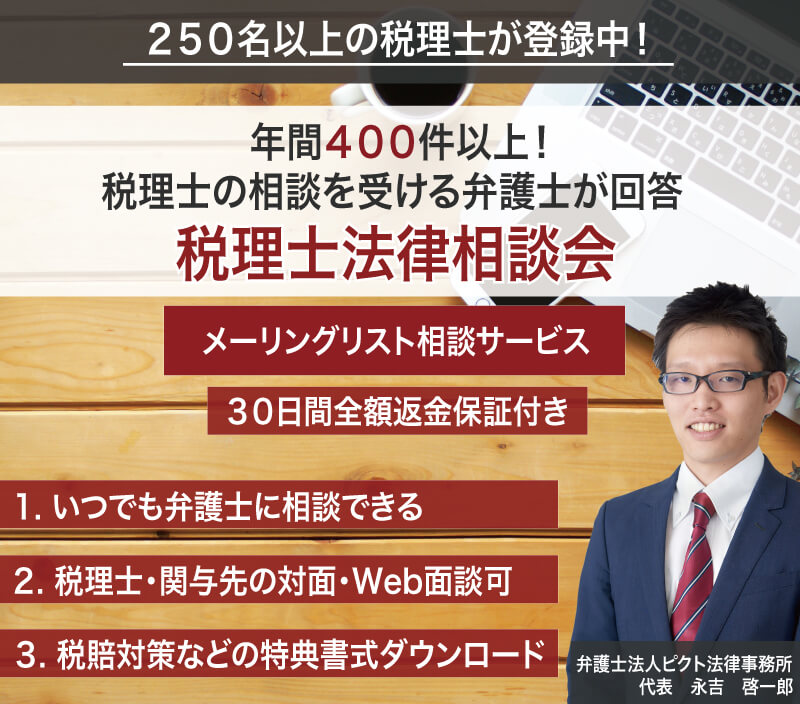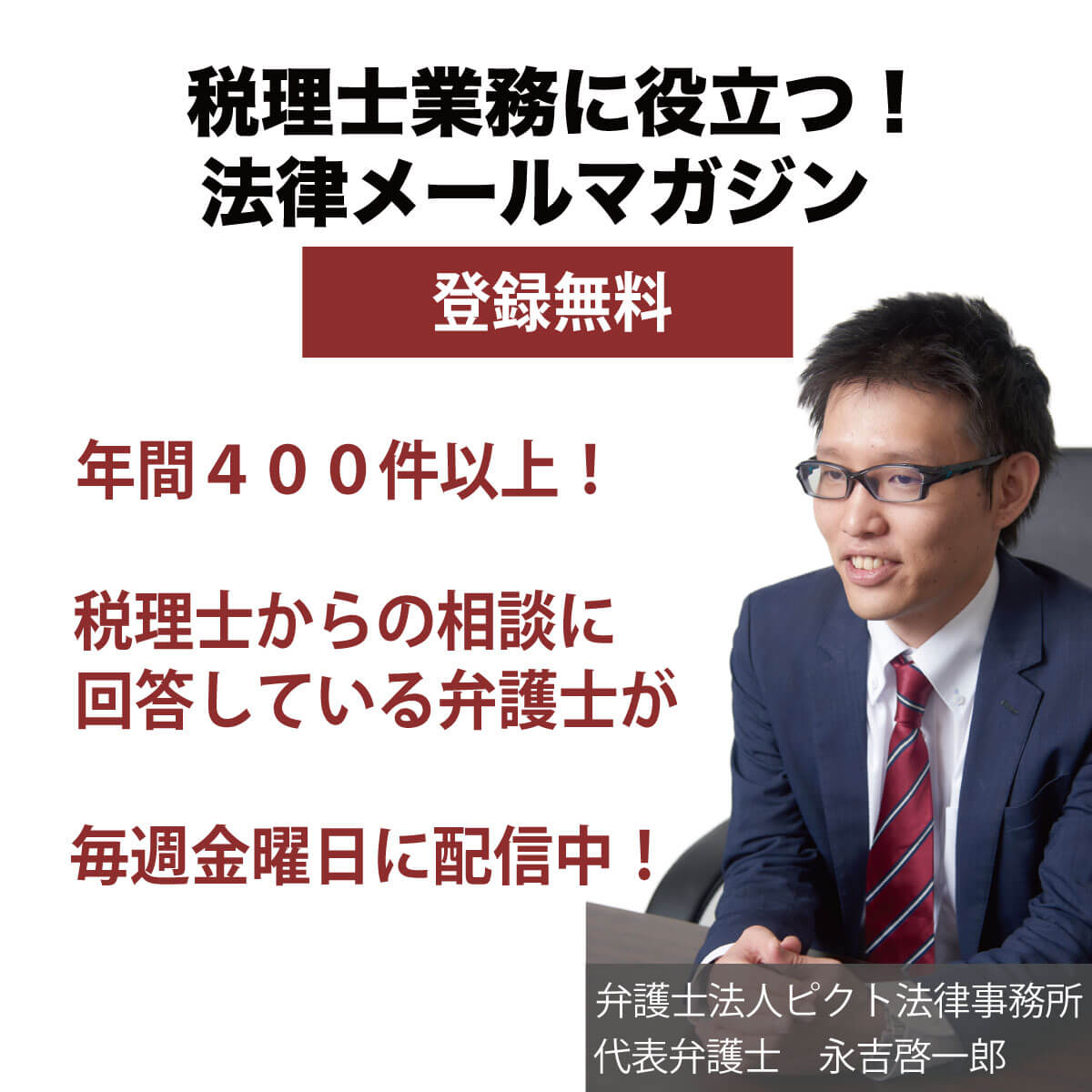遺言の解釈(代償分割か換価分割か疑義がある事例を参考に)〜遺言の法務と税務⑥〜
税理士の先生であれば、遺言書自体をよくご覧になるケースが多いかと思いますが、
その遺言はどのような法的な意味を持つかについては、遺言書の解釈をして確定していくという作業が必要になります。
公正証書遺言であれば、公証人が作成に関与しているため大きな問題がないかとも思われがちですが、時折これはどのように解釈すれば良いのか!?という質問を税理士の先生からいただくこともあります。現実の問題として、相続税や譲渡所得の確定申告にも関わってくる部分ですので、注意が必要です。
例えば、下記の事例については、代償分割と解釈すべきか換価分割と解釈すべきかという点に疑義があります。
◯被相続人甲
◯相続人 長男A 長女B
◯長男Aが、公正証書遺言書第1条第1項の宅地に居住
※注意:疑義がある内容ですので、雛形等に利用しないで下さい。
第1条 遺言者甲は、相続開始時に有する下記の財産を長男Aに相続させる。
(不動産)
(1) 土地
所在 〇〇
・・・
地目 宅地
・・・
(2) 建物
所在 〇〇
・・・
種類 居宅
・・・
(預貯金)
(1) 〇〇銀行〇〇支店
普通預金口座番号 ○○○○○○○
(2) 以下省略
2 長男Aは、前項の財産を取得する代償として、下記の債務を負担するものとする。
前項の財産の全部について、Aは、速やかに換価し、その金額から遺言者の一切の債務及び費用並びに遺言執行者への報酬及びその他一切の費用を控除した残額の中から、遺言者の長女Bに持分割合として、3/10を同人指定の口座に送金する。
第2条・・・省略・・・
第3条(付言事項)
遺言者(私)は、この遺言するにあたり、次のことを申し添えます。
・・・・・・AとBにこのような割合で相続させることとした真意は、これまで生活面での充分なサポートしてくれたAとその妻に財産を残したいという趣旨で、Aに7割の相続させるものです。
この事例を前提に少し遺言の解釈について踏み込んで考えてみましょう。
特例自体の詳述はここでは割愛しますが、以下の特例の適用などにも影響がでるケースかと思いますので、是非ご参考にしていただければと思います。
1 遺言を解釈する際の一般的な判断基準
遺言は、これまでのシリーズでも述べてきた通り、遺言者の意思表示です。
この視点からすると、遺言書はその意思表示を明らかにしたものということになります。
とすれば、契約の場合に、どのような当事者間でどのような意思表示がなされたのかを特定
するように、遺言についても、そのような遺言内容の解釈が必要になります。
特に、遺言は、遺言者の最後の意思表示であって、最高裁も真意を探求すべきと考えています。
下記は、それを明らかにした有名な最高裁判例になります。
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である
2 当該遺言書の解釈
それでは、冒頭の事例における遺言書はどのように判断されるのか見ていきましょう。
2.1 問題点〜代償分割か換価分割か〜
冒頭の事例の遺言書では、第1条第1項のみから判断すると、不動産である土地と建物は、長男Aに対する相続させる旨の遺言であり、長男Aに完全な所有権が移転するというように読むことができます。
問題は第1条第2項です。
第2項も柱書きは、「代償として」下記の債務を負うとされています。とすると、これは長男Aが、不動産などの財産を単独取得する代わりに長女Bに債務を履行するという代償分割になるということになるかとも思えます。
しかし、下記の債務を見ると、不動産を含めた財産を速やかに換価して第三者から金銭を受け取り、3/10を長女Bに支払うということにしています。これは、まさに換価分割を想定しているのではないか?という疑念が生じます。
換価分割の場合には、一旦、不動産の名義のみ長男Aにしておいたとしても、相続人の持分を譲渡し、その対価を持分に応じて、分配するというもので、不動産の第三者への譲渡時の真の所有者は、長男A・長女Bの共有というふうに評価されてしまいます。ですので、上記の2つの特例の適用関係に影響を及ぼすことになります。
2.2 解釈
では、この不動産についての遺言は、代償分割・換価分割どちらなのかということになります。もちろん、事実認定の問題になりますので、唯一絶対の結論ではありませんが、上記の内容ですと、換価分割と判断される可能性が非常に高いと考えられます。なお、換価分割と代償分割の違うはこちらの記事を御覧ください。
本来、代償分割として、債務を負担する場合には、完全に対象財産の所有権を取得しているわけですから、その債務の負担を長男Aの固有財産を原資としようが、他からその金額を借入れて原資としようが、はたまた不動産を売却して、その対価を原資としようが、債務を履行すればその原資については自由なはずです。しかし、今回の遺言書では、不動産を換価することを義務付けられてしまっている点で、代償分割とは認定し難い事情かと思われます。
また、遺言書第2条第2項で「長女Bに持分割合として、3/10」とされています。この「持分割合」という表現は、相続財産が共有になっており、それについての「持分」ということを観念しなければ、利用しない表現かと思われます。そうすると、遺言者の真の意思としては、この意味でも、換価される対象物は共有状態、つまり単独所有となる代償分割ではなく、共有を前提とする換価分割であることを推認される事情になります。
さらに、遺言者がその遺言の真意を伝えるために利用されることのある付言事項についてみると、「AとBにこのような割合で相続させることとした真意は、これまで生活面での充分なサポートしてくれたAとその妻に財産を残したいという趣旨で、Aに7割の相続させるものです。」とされています。
「AとBにこのような割合で相続させることとした真意」と表現しており、遺言者の真意としては、相続財産を7:3で分けますよ、その分配方法として、すべての財産をお金に変えて分け合ってくださいねという意思であったと解釈するのが素直でしょう。つまり、共有物をお金に換えてから7:3で分けねということで、換価分割を想定していると考える強い事情になります。
もちろん、個別事情によりこれを覆すケースもあり得るかとも思いますが、上記の遺言書と最高裁の判例を前提として解釈すれば、この遺言の不動産については、換価分割であると認定される可能性が高いと考えられます。
この遺言書でいうと実際に長男Aが不動産を換価して、7:3で分ければ、民事上は問題ありません。だからこそ、公証人も、あまり問題意識を持たずに認めたということだとも思います。
ただし、税務上の判断として、特例適用の有無などに影響が及び得る点ですので、実はこのあたりは注意が必要です。
3 まとめ
私の肌感覚としては、税務上の問題を考慮し過ぎて、法務上の紛争が解決していないというケースが遺言では多いです(弁護士に来てる案件だからということもかもしれませんが)が、こちらは民事上の問題はあまりないけど、税務に影響を及ぼしてしまっているというケースです。このような事例から考えると、やはり遺言等の対策は、税理士さんと弁護士さんが相互フォローをしながら進めていくことが必要かと思います。
さらに言えば、遺言の解釈は、もちろん実務上の指針はある程度確立されてはいますが、結局のところ事実認定の問題です。疑義ある遺言書がある場合には、最終的には裁判所の認定に依存してしまうというところになります。申告書の提出期限がある税理士の先生であれば、特に判断に悩みを抱えるケースかと思います(その場合は、依頼者さんにリスクを説明した上で、いずれかで申告をするということにはなるのでしょうが)。
ですので、やはり対策としては、遺言書作成の段階から、法務・税務の視点から疑義が生じないようにしっかりと作成していくということが最も重要になるわけです。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日