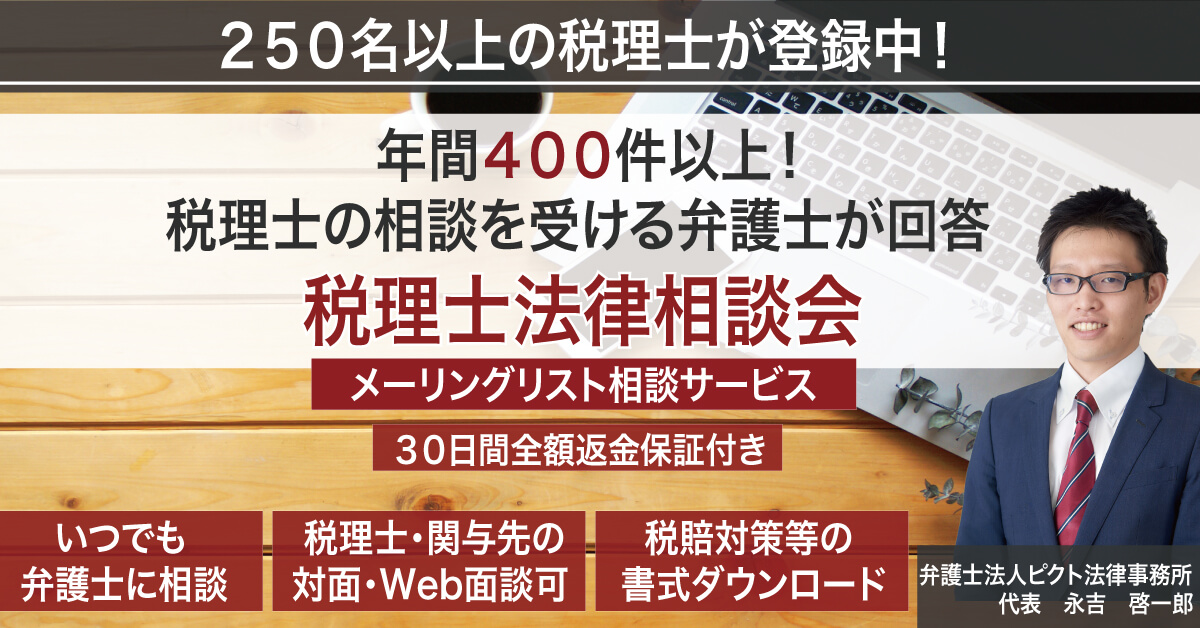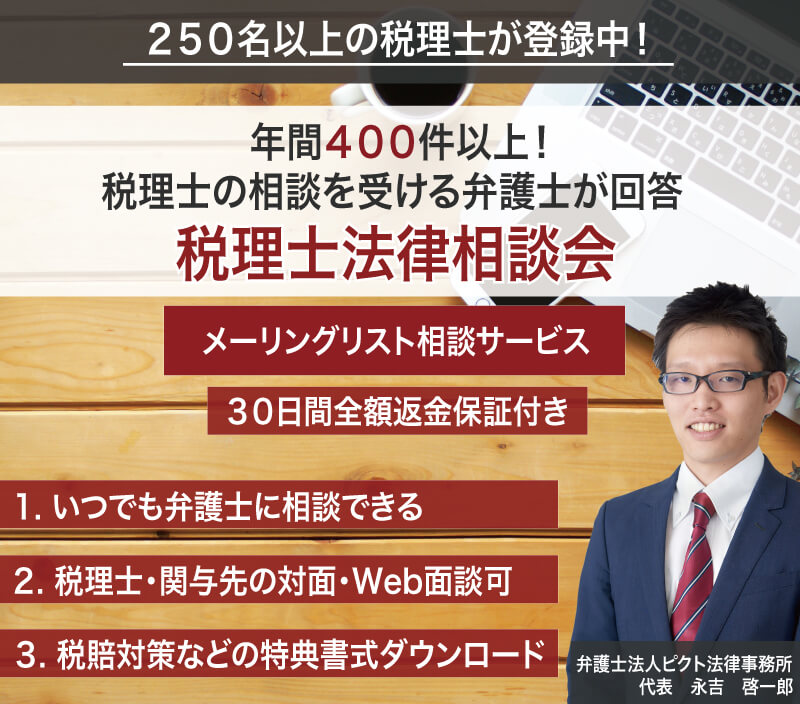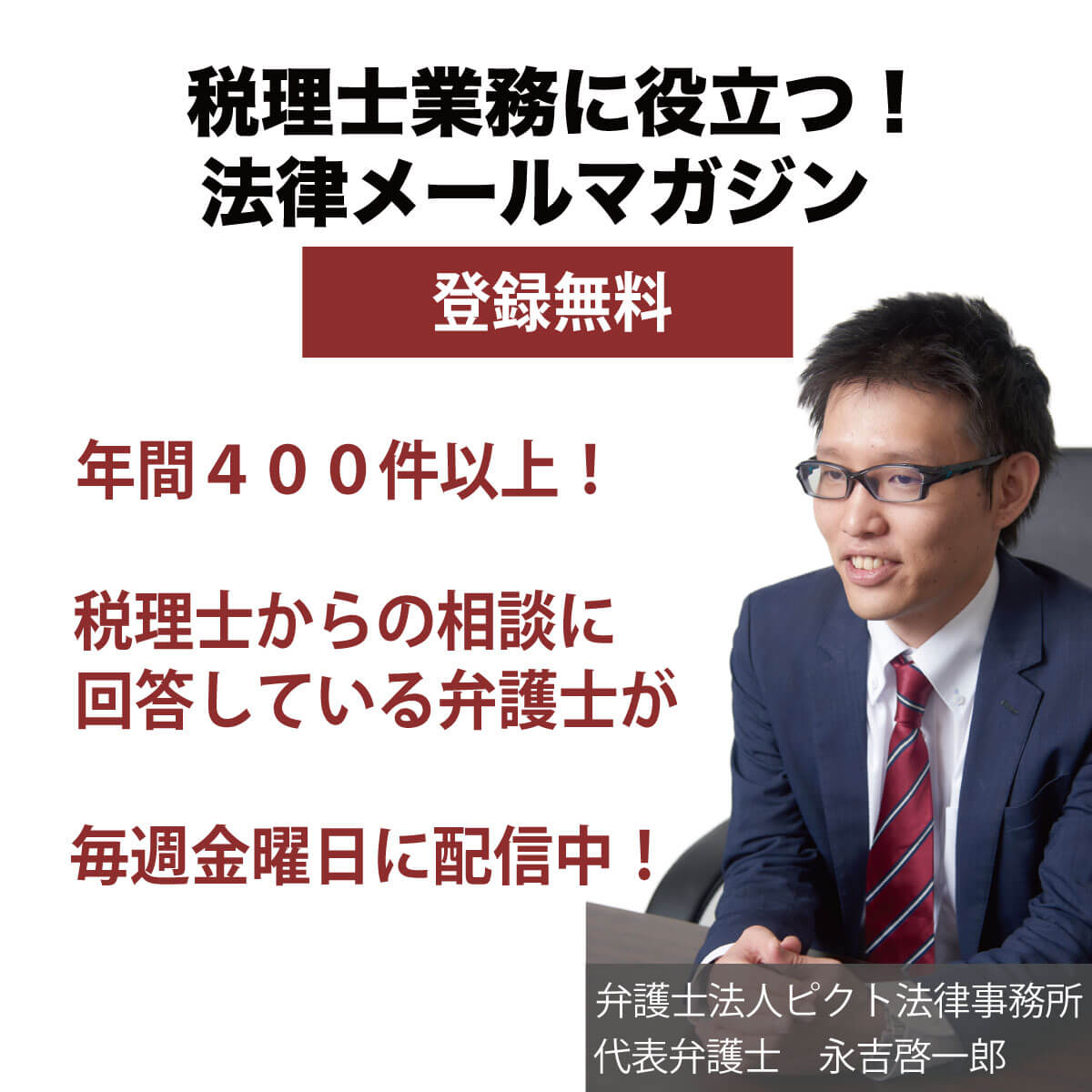遺言の基本的な考え方 〜遺言の法務と税務①〜
今回からは、税理士の先生も、良く遭遇するであろう遺言をシリーズで書きたいと思います。税理士の先生は、相続税対策・申告業務をはじめ、遺言執行者になったりと様々な場面で遺言にでくわすかと思います。この遺言の法的なところを税務上の問題とも合わせて、書きたいと思います。
今回は、シリーズ1発目ということもありますので、遺言の基本的事項や大枠をとらえるという趣旨で書かせていただきます。特に「3」の部分は、今後のシリーズでその内容を詳細に書いていくことになりますので、全体像の把握として、参考にしていただければ幸いです。
【目次】
1 遺言とは!?
まず、税理士の先生には失礼かと思いますが、遺言とは「人の最終の意思表示について、その者の死後に効力を生じさせる制度」というように法律的には説明されています。
なお、余談ですが、「遺言」の読み方は、一般的には「ゆいごん」と読まれますが、法律上は「いごん」と読むとされています。法学部生は、ゼミの教授の前で、「ゆいごん」というと結構怒られます。
2 遺言の基本原則
被相続人の最終の意思表示ということになるのですが、遺言というのはその人が生きているうちの最終の意思を反映させるもので、非常に重要なものであることや相続人の権利関係を一方的に決めてしまうという側面(贈与等の契約なら両者の合意)もありますので、通常の契約や意思表示とは違う面が存在します。ここでは、基本的な遺言の原則を簡単に見ていきましょう。
2.1 遺言自由の原則
まず、遺言は、被相続人の最終の意思を反映させる意思表示になりますので、遺言者が自由な意思に基づき遺言できます。基本的には、この「自由」の意味ですが、以下の2つの意味があると説明されます。
- ①遺言者は、自由にいつでも遺言することができますし、自由に変更すること(民法968条2項、970条2項、982条)、全部または一部を撤回すること(民法1022条)ができます。
贈与等の契約であれば、相手方との合意である以上、このようなことは自由にはできません。また、例えば、遺言者と相続人が、遺言をしないとか、遺言の撤回をしないというような合意をしたとしても、これは遺言自由の原則に反しており、無効となります。 - ②遺産の処理内容について、自由に決定できるという意味があります。つまりは、遺産の一部について遺言をし、残部は法定相続分によるとすることもできるという意味です。
2.2 遺言代理禁止
遺言は、通常の契約等とは異なり、代理人によりすることができません。
なぜかというと、遺言は、人の最終的な意思表示であり、遺言者の意思を尊重することが非常に重要なので、そのように言われています。
遺言による委託とここでいう代理は異なる点がありますので、その辺りの兼ね合いは注意が必要ですが、この部分は、このシリーズで今後解説します。ここでは、代理人による遺言はできないという点を押さえていただければ十分かと思います。
2.3 共同遺言の禁止
2人以上の者が同一の証書で行った遺言(共同遺言)は、民法975条で禁止されており、無効となります。
これは、共同遺言の場合、①2名以上の遺言内容同士がお互いに制約を受けることが多く②遺言の撤回も共同でしなければならなくなり、遺言の自由を保障することが難しいことと③一方の遺言のみの効力に疑義が生じた場合には、他方に影響を及ぼし兼ねないこと等が理由になります。
ただし、ここでは、詳細にまで踏み込みませんが、上記の理由が当てはまらない場合には、有効となる事例もあります。ここは裁判例上も争われているケースも多くあります。例えば、現在の実務上はあまりおこらないと思いますが、全く独立無関係の遺言で、1〜3枚目まではAさんの、4〜5枚目まではBさんの遺言の内容、というようなケースでは、同一の用紙を用いていても、別個のものと評価され、有効と判断されるでしょう。
3 遺言効力を考えるにおいて考慮すべきポイント
上記では、遺言の抽象的な基本原則を見てきました。次に、遺言の効力を考えるにあたって考慮しなければならないポイントを見ていきましょう。このあたりの詳細な実務上の問題等については、今後このシリーズで解説していきますので、今回は、全体像としてこういうものがあるんだなという感じで、みていただければと思います。
3.1 遺言能力
まず、税理士の先生方はご存知の通り、遺言をするには、遺言能力というものが必要になります。
- 遺言能力とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力
と表現されますが、つまりは、ちゃんと遺言の内容を理解できる人でなければいけない、ということです。この遺言能力がない場合に、された遺言は無効となります。
未成年者の場合には、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」(民法961条)とされています。一方、税理士の先生もよく聞くケースかと思いますが、問題は、認知症の(疑いがある)方等のケースです。
このあたりは、裁判例等の紹介をしつつ、このシリーズで書きますので、参考にしていただければと思います。
3.2 遺言方式
遺言は、法律上決められた方式に従わなければ、有効なものとして成立しません(民法960条)。
税理士の先生であれば、遺言が公正証書でされているものを見るのが最も多いかと思いますが、これは、民法969条で、遺言の方式として、公正証書遺言が定められているからです。
他にも自筆証書遺言、秘密証書遺言等々、認められた方式がありますが、メリット・デメリット含めて、詳細を別の記事にて説明します。3.2で言いたかった事は、契約等とは異なり、方式が自由ではないよ、ということです。
3.3 遺言事項
次に、遺言で定めることができる(厳密には定めて効力が発生する)ものは、法律により規定されている事項に限られます。これは、遺言は、上記の通り贈与などの契約とは異なり、一方的に相続人等遺言者以外の人の権利関係を定めてしまうものですので、無制限に認めるとその不利益が大きいことから必要となる要件です。
例えば、一人にすべての財産を与えて、その他の一人に債務を負わせるというのは、債務を負わされた人としてはたまったものではないからです。
なお、実務上、債務の負担を決めるという方法も一定の制限のもと可能です。そちらもまた別の記事にて詳細を書きます。
3.4 遺言の解釈
最後に、遺言は有効だとしても、その遺言の内容が何を意味しているものなのかという点は、遺言の解釈の問題になります。基本的なところでも、代償分割なの?換価分割なの?という疑義がある遺言書もあったりします。このあたりは、税務判断にも関わってくるところです。このシリーズの中で、具体的に税理士の先生からいただいた質問事例を前提に解説していこうと思いますので、そちらも参考にしていただければと思います。
4 まとめ
以上が、遺言の基本的な話になります。今回は、各部分の総論的な説明を遺言の全体像を把握するという趣旨で書かせていただきました。少し税理士の先生には、物足りないものだったかもしれませんが、今後各項目を深め、実務上役立つ形で、解説していければと思っていますので、ぜひ、参考になさってください。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日