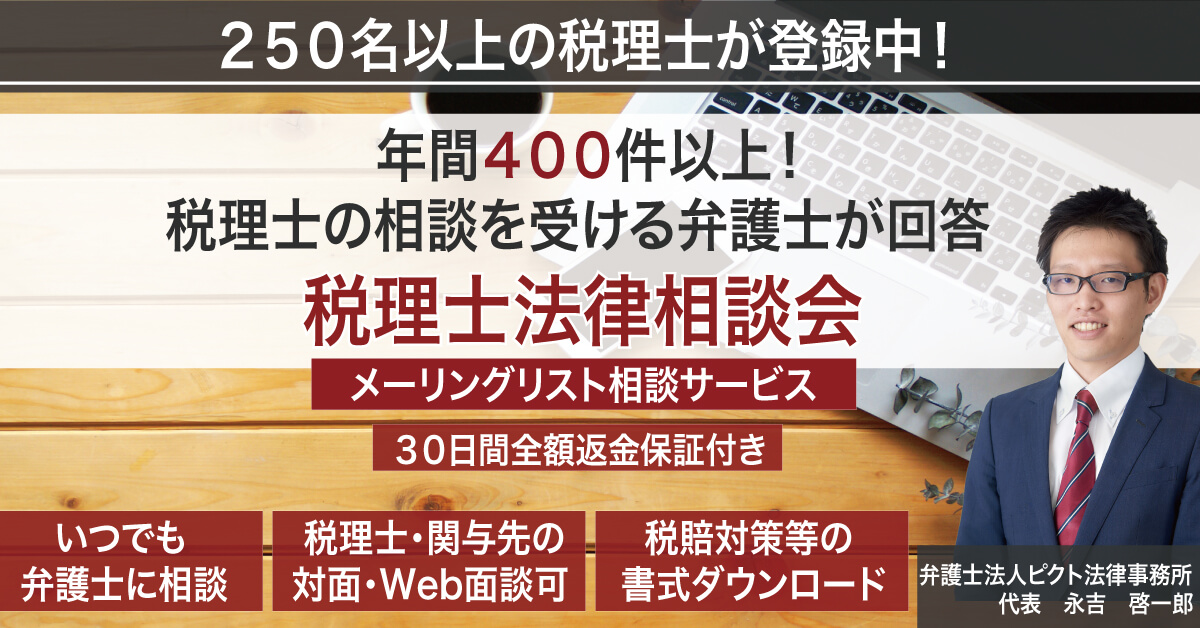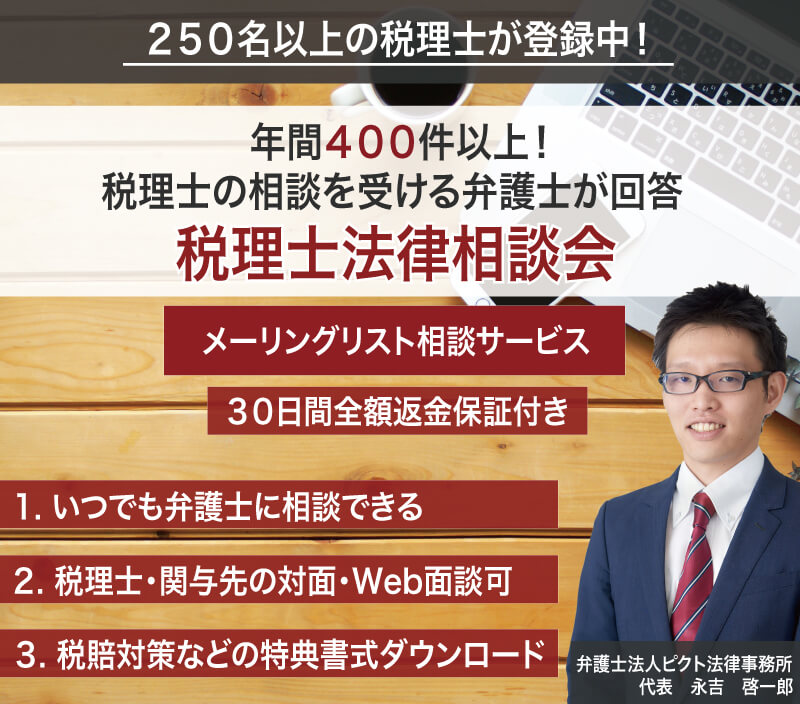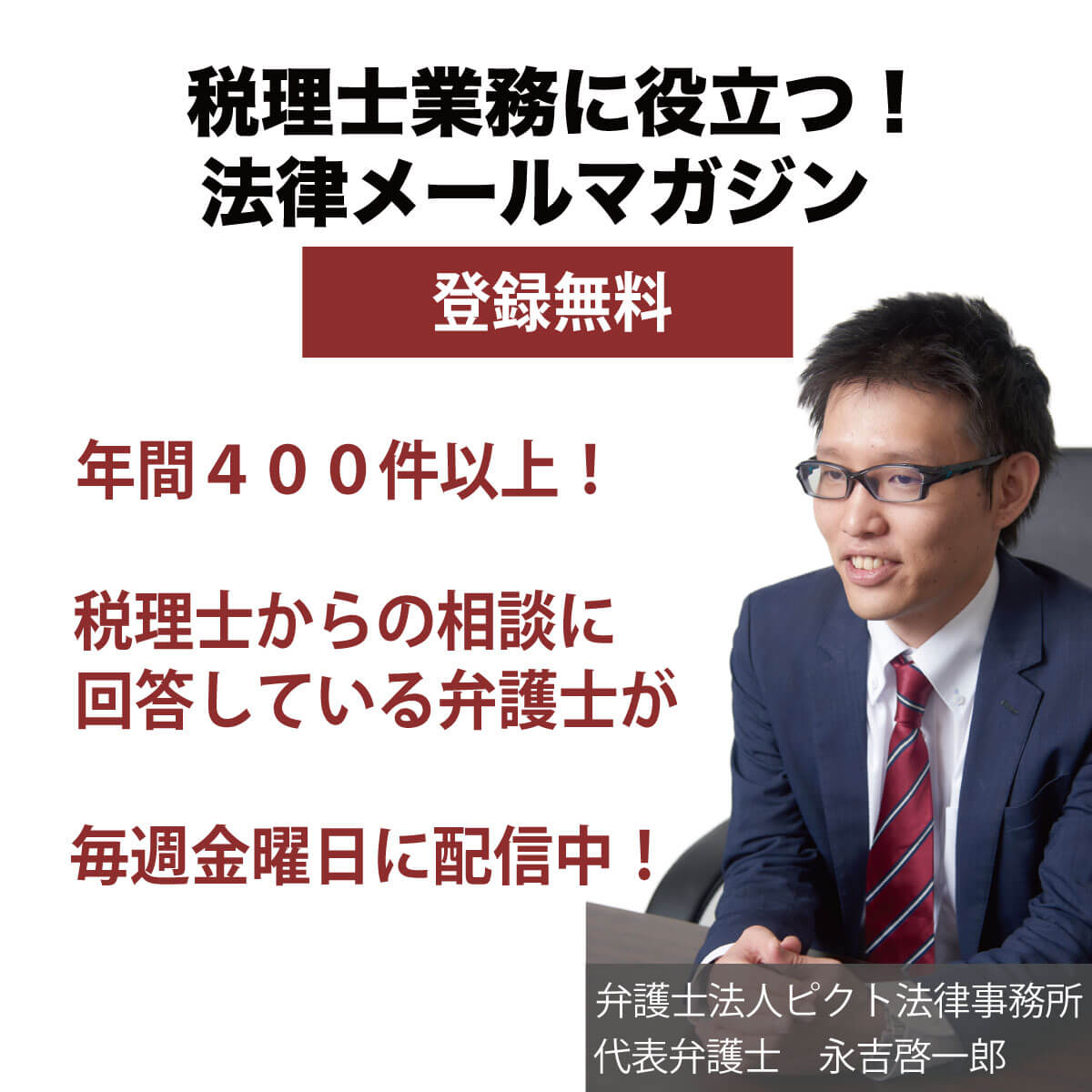遺言についての総合事例検討〜遺言の法務と税務⑧〜
これまで7回にわたって、税理士さんが押さえておくべき遺言に関する法務・税務について解説をしてきました。今回の8回目の記事で、遺言シリーズは一旦終了となります。
シリーズの最後として、今回は、遺言の解釈や撤回など複数の問題を含む事例の検討をしたいと思います。実際に税理士の先生にご相談いただいた事例ですので、ぜひ、ご参考にしてください。
【目次】
1 事例とご質問
◯ 平成X年5月 甲が下記の内容の遺言書作成
・第1条 遺言者は、現金500万円をAに相続させる
・第2条〜第5条 省略
・第6条 遺言者は、第1条ないし第5条に記載した財産を除く財産全部
をDに相続させる
◯ 平成X年12月 Aは、甲から生前贈与で現金600万円を受領する代
わりに以後一切の財産を請求しない旨の誓約書を甲と乙に提出し、
甲から600万円を生前贈与
◯ 平成X+1年4月 甲死亡
◯ 平成X+1年7月 乙とAは、Aが第1条の財産を放棄する旨の確認
なお、その他に相続債務と遺留分侵害はないものとします。
Aが放棄した第1条の財産500万円は、Dに帰属するのか、それとも、未分割財産として、遺産分割の対象になるのか教えてください。
2 法的な論点整理
以上の事例で、最終的な遺言の効果を考えるにあたっては、大きく3つの論点があります。
- ①Aの判断で放棄が可能か?(前提)
- ②遺言者甲の平成X年12月の行為が遺言の撤回行為にあたるか
- ③平成X年12月の行為が、遺言書の解釈に与える影響
の3つです。問題意識について、簡単に見ていきます。
2.1 ①Aの判断で放棄が可能か?(前提)
まず、この税理士の先生には、Aが、平成X年12月と平成X+1年7月に、遺言者や遺言執行者に対して、遺言書第1条の遺言利益を放棄する旨の意思表示をしていますので、Aが遺言の利益を放棄したものという前提でご質問いただいていますが、この遺言の利益の放棄は可能なのかという問題があります。
2.2 ②遺言者甲の平成X年12月の行為が遺言の撤回にあたるか
次に、遺言者甲は、平成X年12月に、甲から現金500万円の相続を放棄する前提で、Aに対して、600万円の生前贈与をしています。この行為は、遺言書第1条と矛盾する行為であり、遺言書第1条を撤回する行為ではないか?が問題となります。
2.3 ③平成X年12月の行為が、遺言書の解釈に与える影響
仮に、②の問題について、遺言の撤回となる場合、税理士の先生のご指摘の通り、第6条をどのように考えるのかが一つ問題になります。
つまり、第1条の撤回に伴って
という問題です。前者であれば、Dに帰属ということになりますし、後者であれば、法定相続分で分けるということになりそうです。
以下では、これらの論点に対して、検討をしていきましょう。
3 論点の検討
それでは、上記の3つの問題について、検討していき、最終的にこの遺言はどのような効力を持つのかという点を明らかにしていきましょう。
3.1 ①放棄の可否
こちらは、問題の前提となるところですが、結論としては、Aの放棄の意思表示については考慮しないということになるかと思われます。
様々議論があるところですが、第1条の規定は、「相続させる旨」の遺言ですので、実務上の先例から、そもそも相続放棄の手続き以外で、相続の放棄はすることができないと考えられています(詳細は、特定遺贈と相続させる旨の遺言との違いについて解説したこちらの記事をご覧ください。)ので、Aが相続放棄手続きをしていない限りは、このAの放棄については考慮しないことになります。
3.2 ②遺言者甲の平成X年12月の行為が遺言の「撤回」に当たるか
次に、遺言の撤回の有無についてです。遺言の撤回・変更のルール・考え方についての詳細はこちらの記事になります。
今回は、生前贈与と第1条の遺言内容が、客観的に矛盾するものではない(両方することも法的にあり得る)事案のため、以下の基準で判断していくことになります。
そして、今回の事例では、遺言者甲の意思を全体で解釈すると、遺言者Aへの生前贈与は、「生前贈与で現金600万円を受領する代わりに以後一切の財産を請求しない旨の誓約書」という文書まで得た上でなされていることからすると、Aへの遺言書第1条の500万円の遺言の内容を撤回する代わりに、Aへ600万円を生前贈与したと考えることが適切でしょう。
ですので、遺言者甲のAに対する生前贈与は、遺言書第1条に「抵触」する生前処分として、第1条は撤回されたものと評価されると考えられます。
なお、類似の参考になる判例として、大審院自体のかなり古いものになりますが、下記のものがあります。
大判昭和18年3月19日
金1万円を与える遺言をした後、遺言者が遺贈に代えて生前に金5,000円を受遺者に贈与することとし、受遺者もその後金銭の要求をしない旨を約束した場合には、「抵触」する。
3.3 ③平成X年12月の事実が、遺言書の解釈に与える影響
最後の論点は、事実認定による難しいものになります。
繰り返しになりますが、②の撤回行為により、遺言書の効果として、遺言書第6条を「第2条ないし第5条に〜」と解釈すべきなのか、または「第1条の財産について、そもそも遺言の対象に含まれなくなった」と解釈すべきなのかという問題です。この現金500万円が、前者であればDに、後者であれば法定相続分による相続人で遺産分割の対象財産になるということになります。
これは、撤回の範囲がどこまで及ぶのかという問題になります。こちらも遺言の解釈のように、遺言書の意思を追求していく作業になります。
結論として、今回の事例では、第6条を「第2条ないし第5条に〜」と解釈し、Dに帰属すると考えられます。理由は以下の事情からです。
- ◯遺言の第6条の記載内容が、「第1条ないし第5条に記載した財産を除く財産全部をDに相続させる」というものであり、指定した財産以外はDに帰属させる趣旨と考えることが文言上素直であること
- ◯誓約書の存在から、甲も遺言に第6条の記載があることを認識した上で、上記抵触行為を行なったと認定することが通常であること
- ◯むしろ、Dは100万円分損をしていることから、遺言者Aとしては、せめて放棄された500万円はDに帰属させるという意思があったと推認できること
以上の事情から、遺言者Aは、第1条の対象分は、Dに帰属させる意思であったと認定できるでしょう。
4 まとめ
以上のように、遺言の効果を考えるにあたっては、事実認定を含む微妙な判断が求められることが多くあります。裁判ではないところで、この意味を厳密に明らかにすることは実は非常に難しいところがあります。特に税理士の先生の場合、遺言執行者になられるケースも少ないくないかと思います。どのように遺言執行をしていくのかにも関係してくる部分で、のちに相続人の紛争に巻き込まれてしまうケースもありますので、ご注意ください。
5 シリーズまとめ
冒頭のとおり、全8回にわたる税理士さんにも押させていただきたい遺言に関するシリーズも一旦今回で終了となります。また、遺言について、税理士さんからご質問をいただいたり、知っていると税理士業務に役立つ内容がある場合には、随時書きたいと思います。長期間ありがとうございました。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日