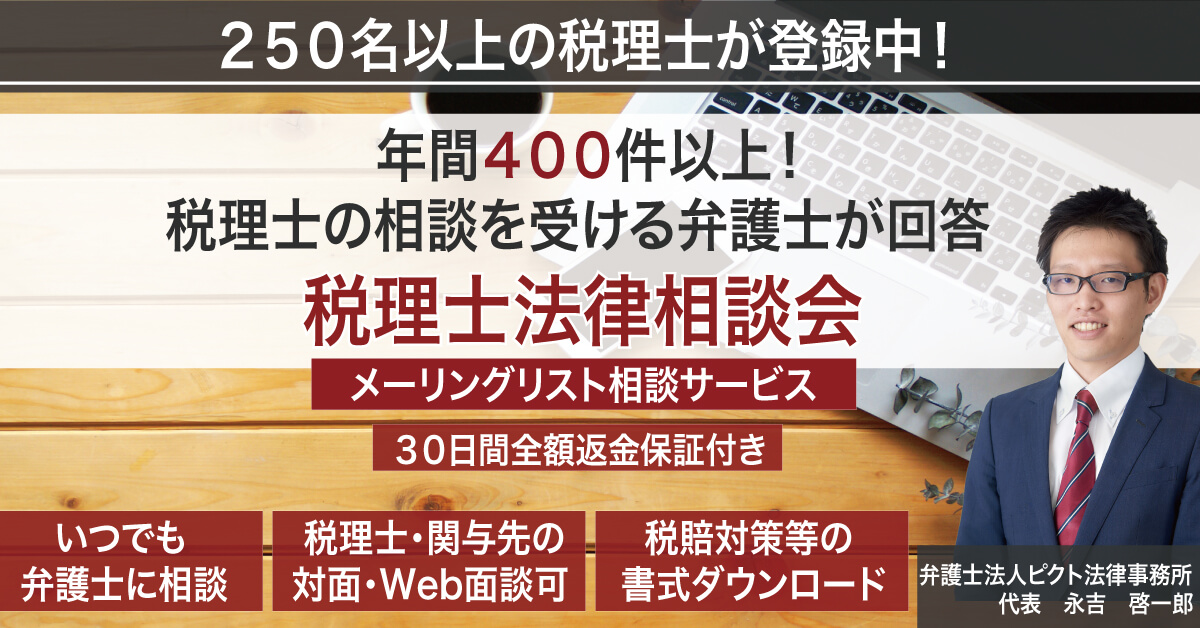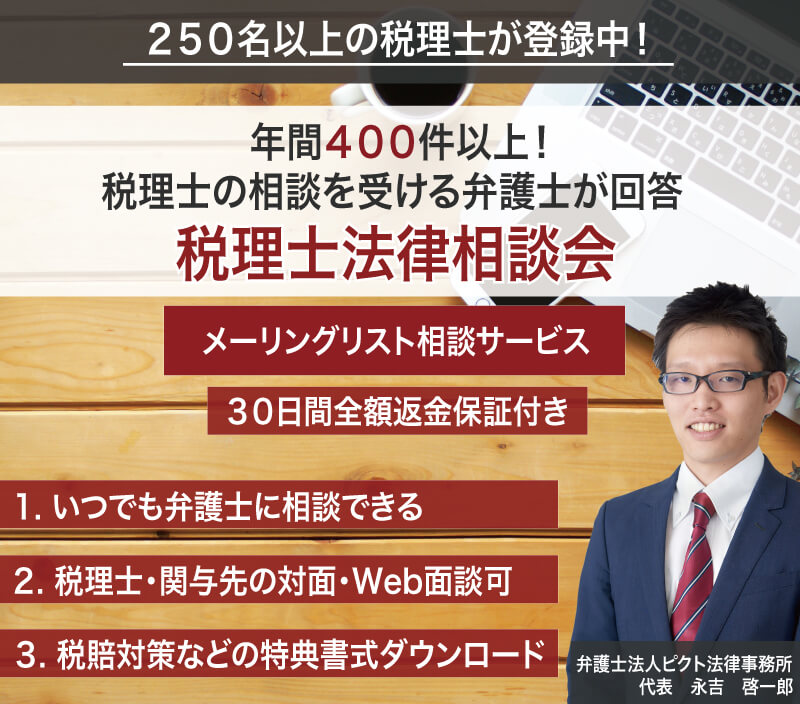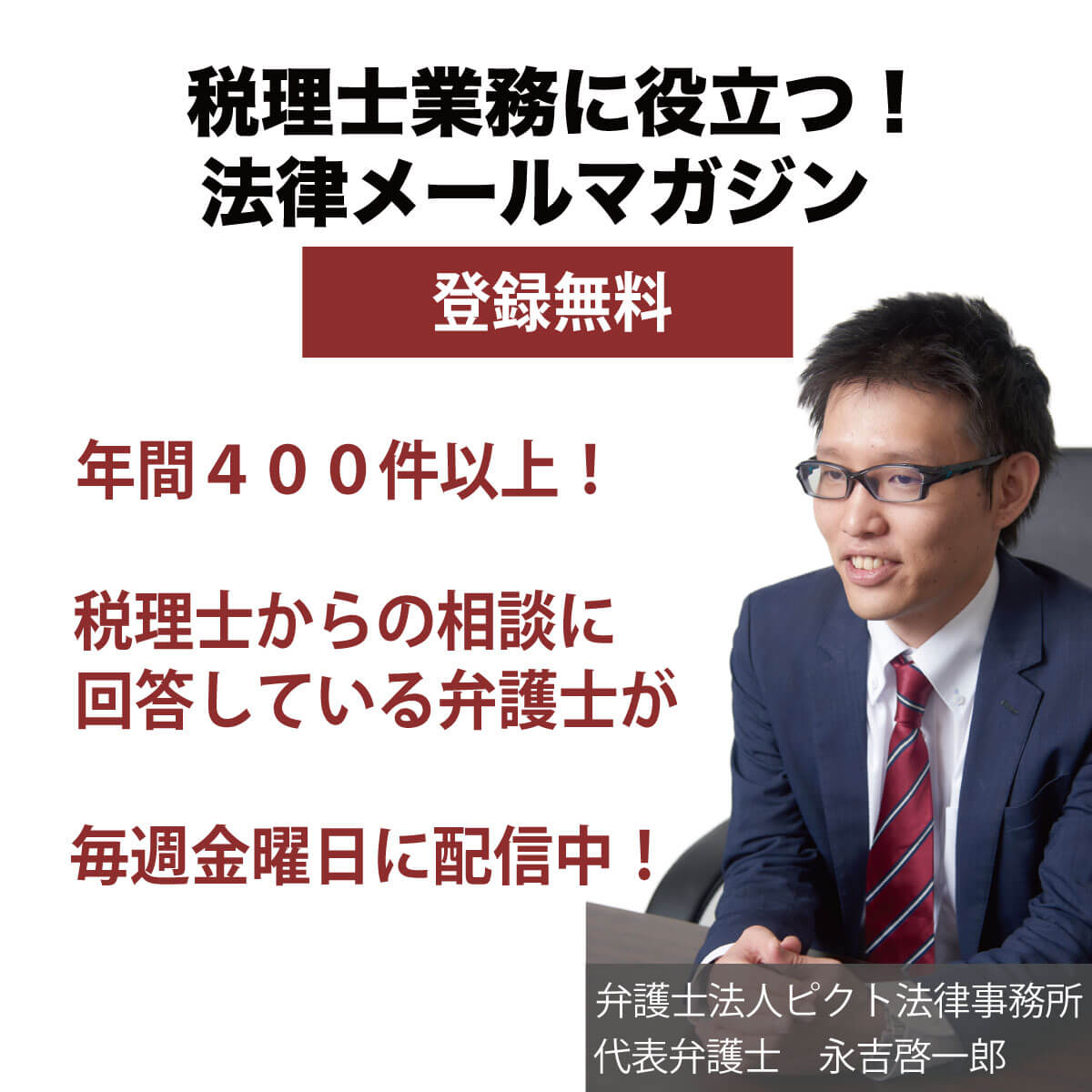遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書・その他特別方式)〜遺言の法務と税務③〜
遺言シリーズの3回目となる今回は、遺言を作成する際に要求させる方式について、書きたいと思います。
【目次】
1 遺言の方式
1回目の遺言の総論に関する記事でも、ご紹介した通り、遺言は、法律上決められた方式に従わなければ、有効なものとして成立しません(民法960条)。
税理士は、公正証書で作成された遺言に遭遇することが一番多いかと思いますが、これは、民法969条で、遺言の方式として、公正証書遺言というものが定められているからです。
遺言の方式には、この公正証書遺言を含む3つの普通方式とそれ以外に特別方式というものが存在します。
1.1 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)
民法第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
普通の方式による遺言は、この条文の本文(「ただし」より前の部分)に描かれている3つの類型があります。いわゆる①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言というものです。
基本的に民法は、遺言がこの3つのいずれの方式をとることを要求しています。各方式の具体的要件は「2」以下で、メリット・デメリット含めご紹介します。
1.2 特別の方式
一方で、上記の民法967条のただし書き(「ただし」以降の部分)には、普通の方式といわれる3つの様式以外でもあっても、「特別の方式」が許される場合、つまり法律上認められる場合には、特別の方式でも良いとされています。
ただし、この特別の方式は、通常ではあまり問題にならない状況下で、例外的に認められるものですので、実務上はほとんど遭遇するケースはないかと思います。この記事では、せっかくですので、「2」以下で、少し詳しく説明します。
2 普通方式
それでは、3つの普通の方式からどのような方式が要求されるのかを見ていきましょう。
2.1 自筆証書遺言
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
条文からもおわかりの通り、自筆遺言証書は、遺言の「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とされております。つまり、本文も手書きでないといけないということになります。
また、自筆証書の場合、本当に遺言者が書いたのか?という点について、疑義が生じやすい(そうであったとしても、本当にそうなのか疑われやすい)ので、その後、争いが生じて、深刻化するケースが多いです。
ですので、実務上は、あくまでも公正証書遺言の作成までの暫定的なものとして捉え、できる限り早く公正証書遺言を作成するべきかと思います。
下記に、各遺言のメリット・デメリットが書いているので、そちらも参考にしてください。
2.2 公正証書遺言
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、遺言書の口述を、公証人が筆記して作成する遺言書です。さらに2名以上の証人も、必要となりますので、遺言の方式の中で、最も確実な遺言書の作成方法です。また、前回の遺言能力の記事でいうところの遺言者の判断能力についても見た上で公証人が作成しますので、その点でも有効なものとして、扱われやすいものになります。
公証人が作成したものであっても、換価分割なのか代償分割なのか等遺言の解釈で、法律的に疑義がある遺言書も存在します。民事上は最終的に誰のものなの?という点さえ決まっていればリスクは高くないのですが、小規模宅地の特例やその後の居住用財産譲渡の特例との関係上、税務上は大きなリスクになるものもありますので、注意が必要です。税理士の先生が遺言に関わる場合には、このような事情もうまく公証人に伝えることも重要かと思います。
2.3 秘密証書遺言
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言は、遺言の内容を、生存中は秘密にしつつ遺言の存在を明確にしておきたいというニーズがある際に用いられるものです。結局のところ、公証人と証人2名以上の関与が必要となる上、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きも必要になります(民法1004条)ので、手間と費用がかかることから、よっぽどの特別な事情がない限りは、公正証書遺言の方が利用されるため、実務上はあまり利用されていません。
2.4 各方式のメリット・デメリット
簡単に普通方式3つを紹介しましたが、以下、各種方式のメリット・デメリットをまとめます。
| 種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付・を自書し、押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう |
| 証人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名/証人2名以上 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 遺言書の開封 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない | 開封手続きは不要 | 必ず家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない |
| メリット | ・作成が簡単かつ安価 ・遺言内容を秘密にできる |
・保管の心配不要 ・遺言の存在と内容を明確にできる ・検認手続き不要 |
・遺言の存在を明確にできる ・遺言内容を秘密にできる |
| デメリット | ・検認手続きが必要 ・紛失のおそれがある ・要件不備(偽造等含む)による紛争が起こりやすい |
・遺言内容が漏れる可能性がある ・遺産が多い場合は費用がかかる |
・検認手続きが必要 ・要件不備による紛争が起こりやすい |
2.5 証人または立会人になれない人
自筆証書遺言を除き、上述の通り、遺言をする場合には、証人や立会人の立会いが必要となります。ただし、誰でも証人などになれるかというと、そうではなく、ちゃんと公正・中立な立場で、判断力のある人でないといけない、ということで、下記の人は証人になれないこととされています。下記の2号は、自分が財産を取得することになる人などは、証人として、中立公正に判断できるか疑いがあるので、そういう人たちを除外するという趣旨です。
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
3 特別の方式
次に、特別の方式です。内容を見てもらえれば、税理士の先生が実務上遭遇するケースはあまりないだろうなということはお分かりいただけるかと思いますが、簡単にご紹介します。
特別方式の遺言は、普通遺言ができないケースを想定して、やむを得ず認められるものですので、遺言者が普通の方式で、遺言をすることができるようになったときから6か月間生存した場合には、その効力は生じなくなります(民法983条)。
3.1 危急時遺言
こちらは、死亡の危険が切迫しており、普通の方式では遺言ができないというようなケースを想定しているものです。
民法上、【Ⅰ】一般的な危急時遺言と、【Ⅱ】船舶が遭難した場合の危急時遺言という2つが規定されています。
【Ⅰ】一般的な危急時遺言
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
病気や怪我により、死の危険が迫っている者についての遺言方式です。
文字が書ける状況の人は、上記普通の方式のうち、自筆証書遺言を作成できるため、
第1項・・・文字が書けない人
第2項・・・口もきけず文字が書けない人
第3項・・・耳が聞こえず文字が書けない人
が、想定されています。
手続きとしては、⑴遺言者が3名以上の証人の1人に遺言の趣旨を口授し、⑵遺言の口授を受けた証人がそれを筆記して、遺言者及び他の 証人に読み聞かせをし、⑶各証人が筆記が正確な事を承認した後、⑷証人がこれに署名押印するという流れになります。また、口がきけない人の場合や耳が聞こえない場合は、上記の通り、第2項、第3項で、通訳人が関与することで、遺言可能としています。
なお、遺言の日から20日以内に証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に対して遺言の確認の請求を行わないと、遺言の効力が生じません(第4項)
【Ⅱ】船舶が遭難した場合の危急時遺言
民法第979条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
こちらは、その名の通り、船舶が遭難した場合において、死亡の危険が切迫した状況にある者が行う遺言です。
このようなケースでは、上記の【Ⅰ】一般的な危急時遺言をすることは困難でしょうから、民法はより方式を簡単にしています。
証人2名以上の立会をもって口頭で行う事ができるようにしています。証人はその趣旨を筆記して署名押印をする必要がありますが、その場で筆記する必要はなく、遭難状態が止んでから筆記する方法でも良いとされています。
ようは、遭難時においては、口頭(または手話)で遺言することを認めているのです。
なお、【Ⅰ】一般的な危急時遺言と同様、その後、家庭裁判所での確認を得なければなりませんが、20日以内に請求するという期間制限は設けられていません。
3.2 隔絶地遺言
こちらは、一般社会に交通ができない(隔離されている等)場所にいる場合に、特別な方式で遺言を認めるものです。民法上、【Ⅲ】伝染病者隔離者等の遺言と、【Ⅳ】船舶中にいる者の遺言という2つが規定されています。
なお、このような者は、普通の方式のうち、公正証書遺言や秘密証書遺言は利用できませんが、自筆証書遺言をすることは可能なので、これらを利用することは、ほとんど想定できないかと思います。
【Ⅲ】伝染病者隔離者等の遺言
民法第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
こちらの規定では、「伝染病」とされていますが、この規定は、一般社会との交わりが物理的に取れない場所にいる人も含むと解されています。例えば、刑務所にいる者、災害により交通が遮断される場所にいる者も含みます。
こちらでは、遺言書の作成が必要になり、遺言者の署名・押印も必要とされます(民法980条)。なお、遺言者が病気等で、自署ができない場合には、立会人または証人がその理由を遺言書に記入する必要があります(民法981条)。
【Ⅳ】船舶中にいる者の遺言
民法第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
条文の通りです。遺言者の署名・押印が必要で、病気等で自署できない場合には立会人または証人がその理由を遺言書に記入する必要があるのは、【Ⅲ】伝染病者隔離者等の遺言の場合と同じです。
4 まとめ
以上が、遺言に必要な方式になります。基本的には、公正証書遺言を残すことが、最も確実な方法ということになります。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日