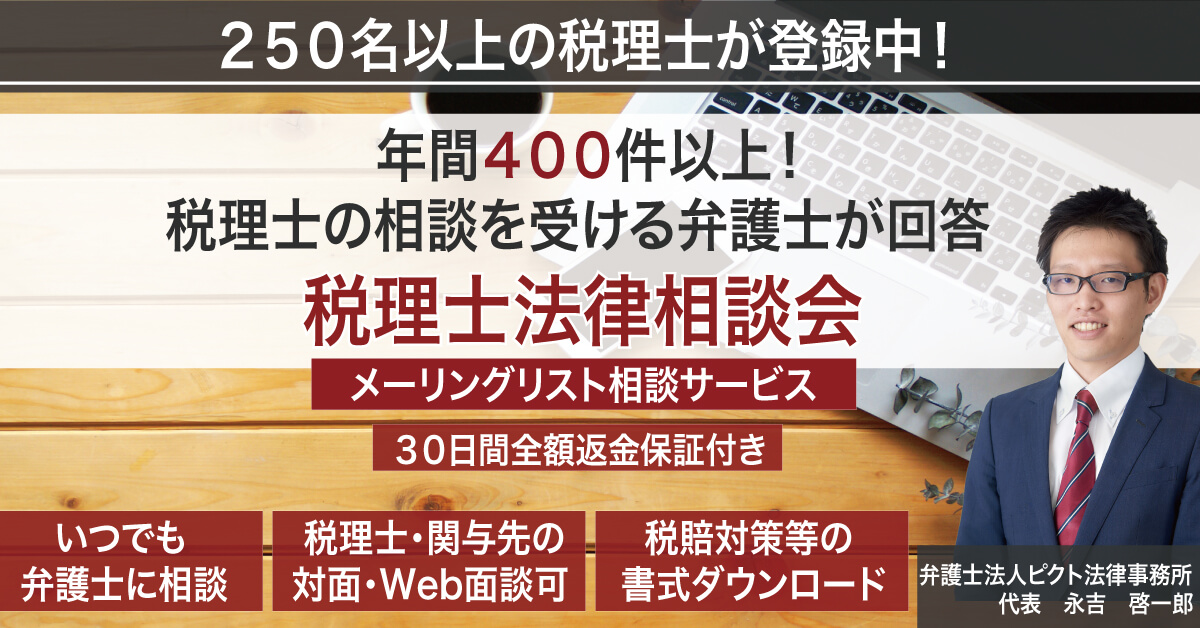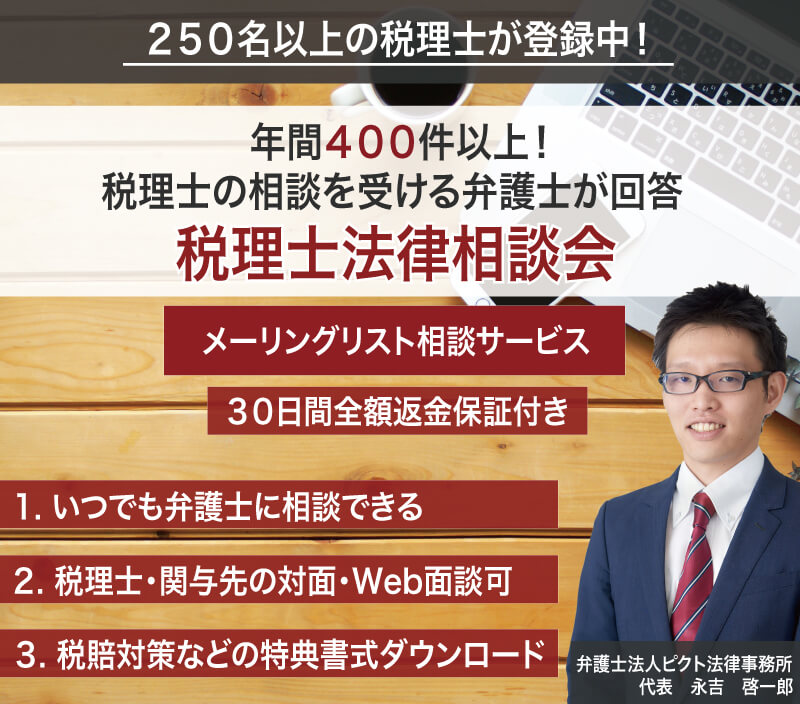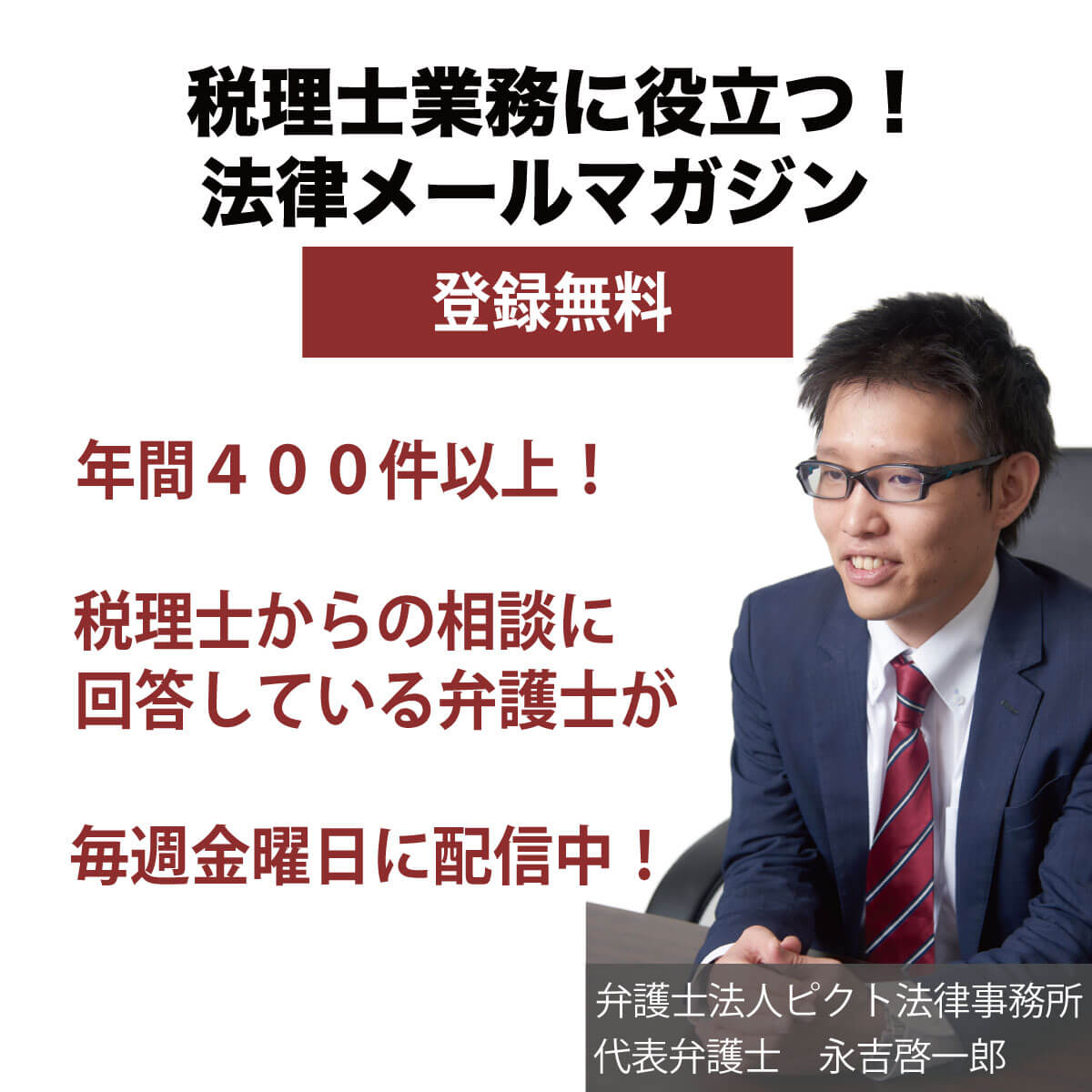特定遺贈と相続させる旨の遺言の違い〜遺言の法務と税務⑤〜
前回から遺言事項に関する記事を書いており、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、相続させる旨の遺言などの遺言事項についての一般的な説明をさせていただきました。
今回は、その中でも似て非なるものである特定遺贈と相続させる旨の遺言の違いを解説したいと思います。いずれの遺言に当たるかで、相続税申告にも影響がでますので、ぜひご参考にしていただきたいと思います。
【目次】
1 相続させる旨の遺言と特定遺贈の共通点
まず、特定遺贈と相続させる旨の遺言を、混同しやすい理由として、大きな共有点があるということがあります。それは、遺言の効力により、ある特定の財産の所有権等特定の権利を移転させる効果を持つという点です。
例えば、「不動産Aを甲に相続させる。」、「不動産Aを甲に遺贈する。」などであれば、いずれの場合も、不動産をAを遺言によって甲に帰属させる効果を持ちます。
2 相続させる旨の遺言と特定遺贈の異なる点
このような共通点のある「相続させる旨の遺言」と特「定遺贈」ですが、法的効果を考える際に違いが生じます。
主な違いは、相続させる旨の遺言は、あくまでも「相続」であり、包括(一般)承継である一方、特定遺贈は、特定承継であるというところから生じます(【包括承継と特定承継の違いについての記事】)。
つまりは、相続される旨の遺言(包括承継)では、被相続人とあたかも同じ人のように権利義務を引き継ぐことになりますが、特定遺贈(特定承継)では、被相続人と受遺者との関係で贈与等の契約があったものに近い譲渡されるということになります。
以下は、相続させる旨の遺言と特定遺贈の主な具体的な違いが現れる場面をご紹介します。
2.1 対象者
まず、相続させる旨の遺言では、その名の通り、「相続」ですから、相続人にしか行うことができません。
一方、特定遺贈は、上記のように特定承継を生じさせる行為ですので、基本的には誰に対してもすることができます。もちろん、相続人に対する特定遺贈も可能なわけです。
2.2 単独登記の可否
例えば、特定の不動産Aを甲に相続させるまたは遺贈するという場合には、当然ですがその後、不動産の登記名義を甲に移転する必要があります。
そのような場合、相続させる旨の遺言では、不動産Aと不動産Aの所有者であり遺言者であるという被相続人の地位を、甲が包括承継します。ですので、登記をする場合には、基本的に元所有者と新所有者両名が協力する必要があるのですが、その両名の地位が同一人物である甲に包括承継されることから、甲は単独で登記手続きを完了することができます。
一方で、特定遺贈の場合には、特定承継ですので、例えば不動産の売買があった場合でいう売主と買主が協力して、登記をするという形と同じになります。つまり、遺贈者としての被相続人の協力義務を、甲を含めた相続人「全員」が承継しますので、その他の相続人と受遺者である甲が協力して、登記手続きを完了しなければなりません。
この場合、法律上は、他の相続人も協力義務を負いますので、問題がないように思えますが、相続の場面(特に遺言がある場面)では、他の相続人が甲に対して、よくない感情を持っているということもあるので、稀に手続きが進まないこともあるのです。なお、この問題は遺言執行者を選任しておくことで回避できますので、できれば遺言執行者は定めておいた方が良いでしょう。
2.3 借地・借家権など
土地や建物を賃貸借で借りていた場合、被相続人が死亡しても、賃貸借の契約関係は存続します。その際に、この借地権や借家権をある特定の相続人に相続させるまたは遺贈させる場合です。
この場合、法理論的には、「相続させる」であれば、当然に賃借人である地位も包括承継しますので、賃貸人の承諾を得る必要はありません。一方、「特定遺贈」であれば、これは特定承継、つまり権利の譲渡にあたりますので、賃貸人の承諾を得なければ賃借人の地位を承継できないということも考えられるのです。
2.4 第三者への対抗力
特定の不動産Aを甲に相続させる旨の遺言では、甲以外の相続人の債権者などの第三者が、その不動産のその相続人の持分に対して、仮差押えおよび差押えをした対抗要件を備えた場合、甲は不動産Aの相続による取得の登記をしていなかったとしても、この第三者に対して、その他の相続人の法定相続分を自己の所有であることを主張することができるとされています。なお、【対抗要件についてはこちらの記事】をご覧ください。
つまりは、特定の財産を特定の相続人に対して、相続させる旨の遺言の効果は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により包括承継されるされている(最高裁平成3年4月19日)ことから、そもそも、その他の相続人に対して対象財産の法定相続分の移転が観念できなため、第三者の対抗要件は、無効であるというふうに判断されます(最高裁平成14年6月10日)。
一方、特定遺贈の場合、上述の通り、特定承継であることを理由に下記のように考えられています。
-
最判昭和39年3月6日
-
「遺贈は遺言によって受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず、遺言者の死亡を不確定期限とするものではあるが、意思表示によって物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはないのであるから、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とする所有権移転登記がなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じないものと解すべきである。そして、民法177条が広く物権の得喪変更について登記をもって対抗要件としているところから見れば、遺贈をもってその例外とする理由はないから、遺贈の場合においても不
動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきである
として、登記を得なければ、第三者に遺贈の効力を対抗することができないとされています。
2.5 遺言の利益の放棄
まずは、特定遺贈の場合には、受贈者は、遺言者の死亡後、その遺贈を受けることを放棄することが可能です。
(遺贈の放棄)
民法第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
しかし、相続させる旨の遺言では、特段の事情なき限り、あくまでも「相続」ですので、その遺言の利益を放棄するには、相続放棄手続きによる必要があるとされ、学説上は様々な議論があるところですが、裁判例上は、遺言利益のみの放棄は認められないと考えられています(東京高裁平成21年12月18日)。なお、遺産分割協議で相続人全員で合意形成できれば調整をすること自体は可能です。
2.6 相続債務の取り扱い
原則的に、特定遺贈の場合には、特定の積極財産を移転させるというものですので、特定遺贈の影響を受けて、受遺者が相続債務を負うということはありません。ただし、特定遺贈の場合にも、「負担付」遺贈というものがあります。この方法により、移転される特定の積極財産の価格の範囲で、相続債務を受遺者に負担させるという方法も可能です。
(負担付遺贈)
民法第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
一方で、相続させる旨の遺言です。こちらも特定の積極財産を移転させるものではありますが、その性質として、遺産分割方法の指定と併せて、「相続分の指定」が伴うと解釈させることがあります。
-
最高裁平成21年3月24日(下線:筆者)
- 本件のように,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である
この判例は、「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合」という特殊なケースということで、その射程がどこまで及ぶのかという点は実務家によって見方が異なるところがあります。ただし、積極財産の各相続人に相続させる旨の遺言があった場合には、遺言に何か特別な定めや特別の事情がなければ、相続分の指定を伴うものとして、その割合に応じて、相続債務の負担割合が決まるという考えが相続法全体のバランスとしても適切という意見が強いですし、私もその見解です。もちろん、最終的には、その事案におけるその遺言の意味の解釈の問題になってしまいますが。
また、上記の「相続分の指定」が伴うのか、という議論とは別に、実務上は、ある特定財産に紐付ける形の「負担付相続させる旨の遺言」も、上記民法1002条を準用して、有効と扱われています。例えば、ある建物を相続させることに付随して、その建物にかかる住宅ローンを負担とするという例があります。この場合は、相続税申告の場合、債務控除というよりは、財産評価(負担額を差引く)の中の問題となります。
2.7 ※遺言の効力発生前の受遺者の死亡時の代襲相続に注意
相続させる旨の遺言の場合、あくまでも「相続」ということで、遺言の効力発生前の受遺者の死亡した場合は、通常の相続人が死亡すれば、代襲相続が発生するのであるから、このようなケースでも、代襲相続が発生するのではないか?と理論上は考え得るところでは、あります。
しかし、この点は、下記の判例があります。
-
最高裁平成23年2月22日(下線:筆者)
- 「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
つまりは、受遺者が死亡した場合に、代襲相続人に相続させる特別の事情(条項があるなど)がない限りは、特定遺贈の場合と同様に代襲相続は発生せず、その部分は遺言の効力が失われます。
このような考え方からすれば、遺言書を作成するとき、特に年齢の近い配偶者へ自宅建物などを移転させる場合には、仮にその配偶者が亡くなったときにその財産を誰に移転させるのかは、明確に定めておいた方が良いかと思われます。
3 まとめ
以上が、特定の財産を特定の相続人に対して、相続させる旨の遺言及び特定遺贈をした場合の違いになります。裁判例上の分析からはこのようになるのですが、正直「相続させる」と書いたのか、「遺贈」と書いたのかでこのような違いが生じてしまう最高裁の判断が、実務上の判断基準として妥当なのかというと、個人的には、おかしくない!?と思っています(もちろん、これまでの経緯・歴史などを見るとしょうがないのかなという思いもありますが。)。
もちろん、最終的には、その事案におけるその遺言がどうなのか(特段の事情などの判断)ということになり、最後は裁判で白黒つけるということですが、相続税申告にも影響がある以上、税理士の先生の立場としては、このあたりを事前に判断しなくてはならないという難しさがあります。
この辺りは、現在進行している相続法の改正の流れから、ちゃんと整理してもらえるとありがたいなと思っています。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日