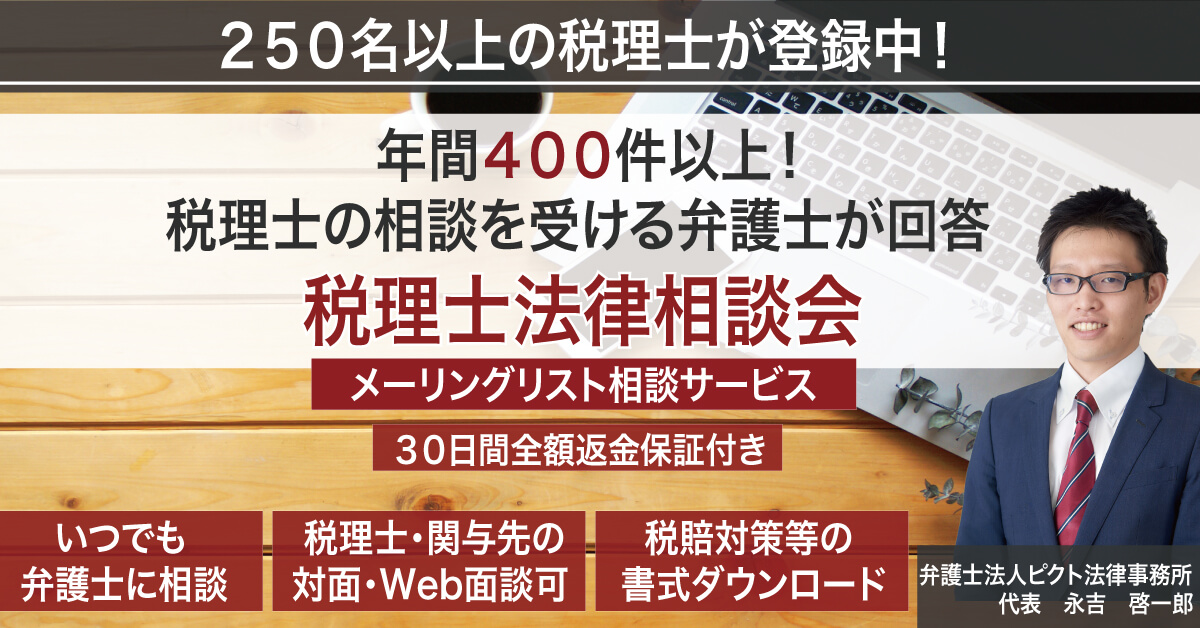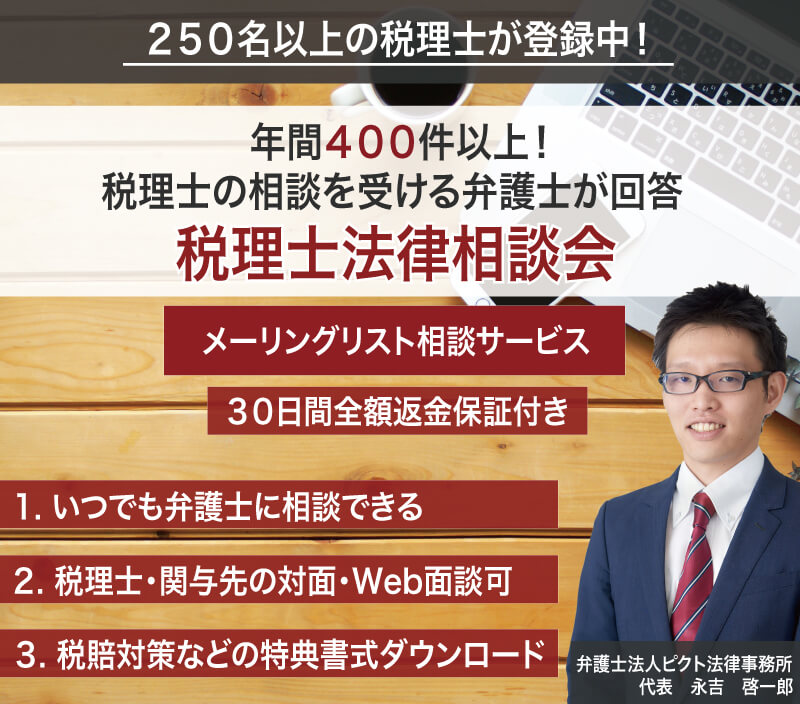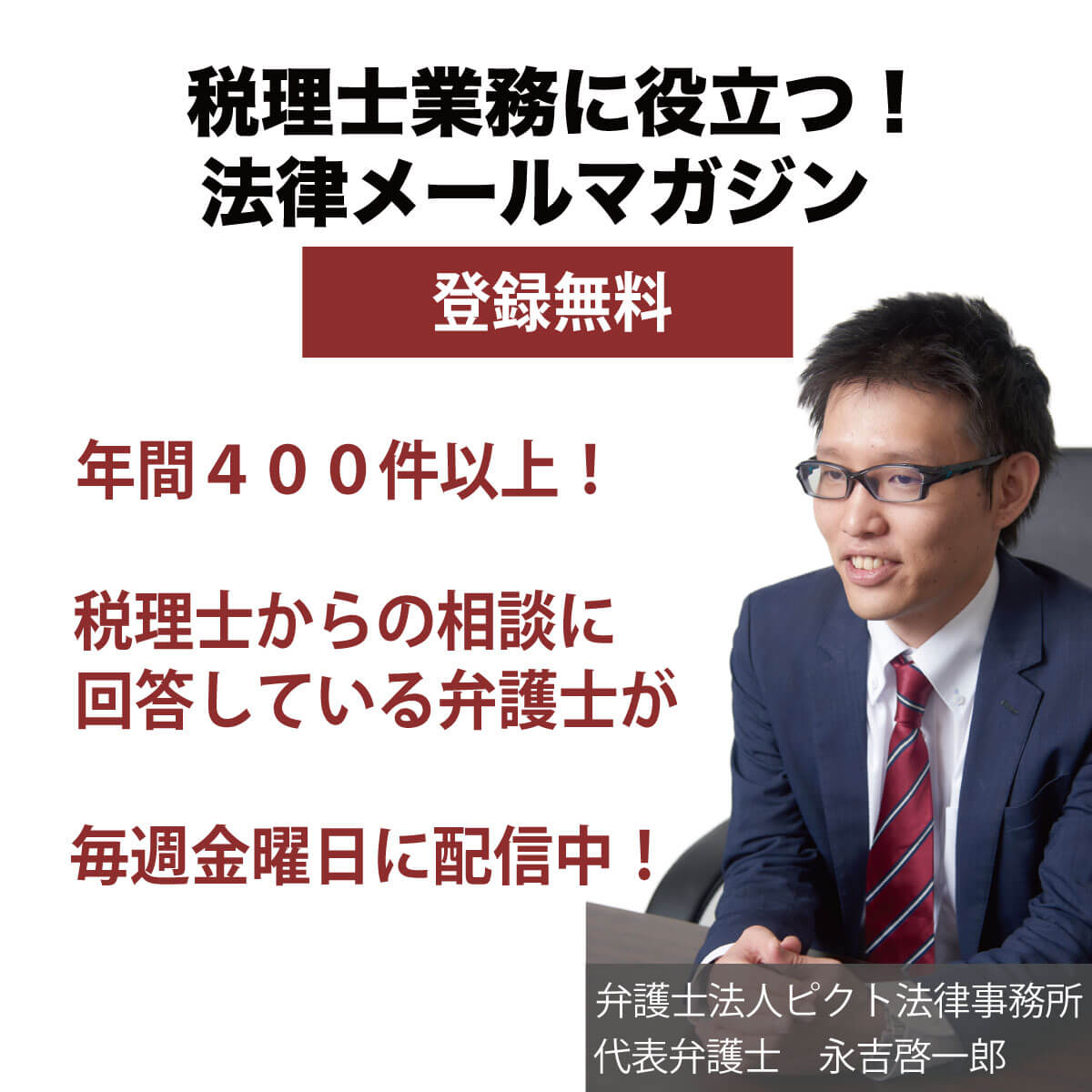税法解釈の方法〜侵害規範と借用概念〜
当サイトでは、税理士の先生向けに、税理士の先生が知っておいたら役に立つ法律に関する知識や知恵を発信しています。今回は、税法の解釈にはどのようになされるのかという点を、一般の法解釈の方法と比較しながら書いてみたいと思います。今回は、税理士の先生には説明するまでもない内容かもしれませんが、基本を思い出す意味でもご参考にしていただければ幸いです。
1 一般法解釈
法学の教科書等を見ると様々な学者の先生が様々な意味で、解釈方法に名前つけて解説しています。概ね一般的かと思われる例を挙げると以下のものになるかと思います。
| 1. 文理解釈 | 法文や文言から解釈する方法 |
|---|
| 2. 目的論解釈 | 法の趣旨や目的を実現するため |
|---|---|
| 拡張解釈 | 文言を通常の意味より拡張して解釈 |
| 縮小解釈 | 文言を通常の意味より縮小して解釈 |
| 類推解釈 | 本来の適用場面とは異なるが、あえ て適用する解釈 |
等々があります。
つまりは、本来的には文理解釈になりそうですが、立法段階で、実際その表現が全ての事象を考慮して作ることは不可能ですし、あまり具体的にし過ぎると今度は、規制すべきものができなくなったりするので、法律といっても、完璧には作れません。
特に今は、世の中の変化も速いので、すぐに法律の直接的な規定が見つからないビジネス等色々とでてきます。
そこで、文理解釈のみではなく、目的論解釈等も行い現実に合わせた解釈をしていくことになるということですね。
抽象的になってしまいますが、現実には、文言の国語的意味、その条文自体やその法令全体の趣旨・目的、社会的・政治的・経済的諸条件、結論の妥当性及び公平性等を考慮して、解釈していくことになります。
2 税法固有の解釈に関する問題
ただし、税法を解釈する場合には、別途考慮すべき点があります。そうです。租税法律主義(憲法84条)ですよね。
文理解釈の重視
租税法律主義の趣旨は、課税が国民の「財産権」(憲法29条)を侵害するいわゆる「侵害規範」にあたることから、国民を代表する国会が制定した法律で課税の条件等を決定しなくてはいけないという点にあります。
そこで、文言からあまりにもかけ離れた解釈が許されてしまうと、その趣旨が全うされなくなってしまいます。
そこで、課税要件の解釈等を行う際には、できる限り「文理解釈」をとるべきということになります。上にあげた拡張解釈や類推解釈をすることは避けるべきということになるかと思います。
もちろん、要件が一定の曖昧さを持つことはやむを得ない部分もありますので、そのような際には、立法の趣旨・目的を勘案した上で、その文言を確定していくということになるでしょう。
このような文理解釈を重視する判例として、下記の「ホステス源泉徴収事件」があります。これは、所得税法施行令322条が、ホステスの源泉徴収金額から控除可能な額の計算方法として、「5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」を定めているのですが、課税庁がこの「期間」の意味を現実にホステスが出勤した日であるという主張をしていた事案です。
「一般に,「期間」とは,ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった,時的連続性を持った概念であると解されているから,施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間」も,当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり,これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない」とし、「租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではない。」
として、計算の基礎となる「期間」は現実に出勤した日をいうのではないとしました。
借用概念論
以前にも紹介しました(借用概念に関連する記事)が借用概念論とは、租税法上に言葉の意味が規定されていない場合に、その他の法律で同じ言葉が使われている規定がある場合には、特別な事情がない限り、その他の法律と同じ意味で解釈すべきという考え方(判例・通説)です。
これも、他の法律では、別の意味で解釈されているものを、税法上のみ(法律で別途規定が置かれているものは除く)別の意味で解釈されるということになれば、国民はどの解釈を前提に判断すれば良いかわからなくなります。そのような解釈を認めてしまえば、解釈に特殊な立法に近い機能を持たせることになり、上記の租税法律主義の趣旨が全うできないからです。
この借用概念については、かの有名な「武富士事件」についての最高裁判決があります。現在は立法で解決されている問題ですが、相続税法の「住所」の解釈について、高等裁判所は、民法上の「住所」の解釈である「客観的な」生活の本拠たる実体があるか否かのみではなく、居住意思という「主観的な要素」も加味すべきとして、租税回避目的で海外への滞在期間等を調整する意図があり、相続税法上の「住所」は国内にあるという判断をしました。
それに対して、最高裁は、下記のように民法と同じように、客観的に生活の本拠たる実体を具備するかで「住所」に当たるかを判断すべきとして、高裁の判断を否定しました。下記に最高裁の判決文を引用しますが、下線のみお読みいただければ趣旨は分かるかと思います。
法1条の2によれば,贈与により取得した財産が国外にあるものである場合には,受贈者が当該贈与を受けた時において国内に住所を有することが,当該贈与についての贈与税の課税要件とされている(同条1号)ところ,ここにいう住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由はない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第412号同年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年(オ)第552号同年9月13日第二小法廷判決・裁判集民事27号801頁,最高裁昭和35年(オ)第84号同年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁参照)
・・・略・・・
法が民法上の概念である「住所」を用いて課税要件を定めているため,本件の争点が上記「住所」概念の解釈適用の問題となることから導かれる帰結であるといわざるを得ず,他方,贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり,このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば,法の解釈では限界があるので,そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。
3 まとめ
以上が、一般の法解釈手法と比べて、租税法を解釈する際には特別の考慮が必要なことについての説明になります。
現実の税務実務上、本当にこの考え方がしっかりと貫かれているのかという問題が残るケースもありますが、税理士の先生としては、租税法はこのように解釈すべきであるというところを調査官に反論する場面もあるかと思いますので、是非ご参考にしていただければと思います。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日