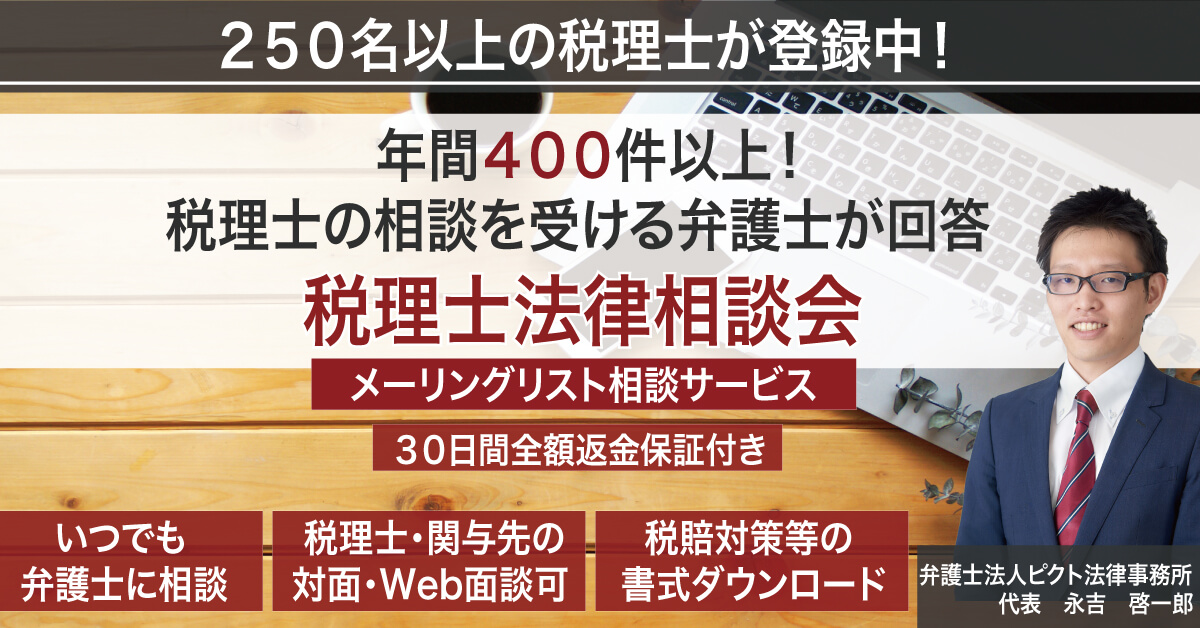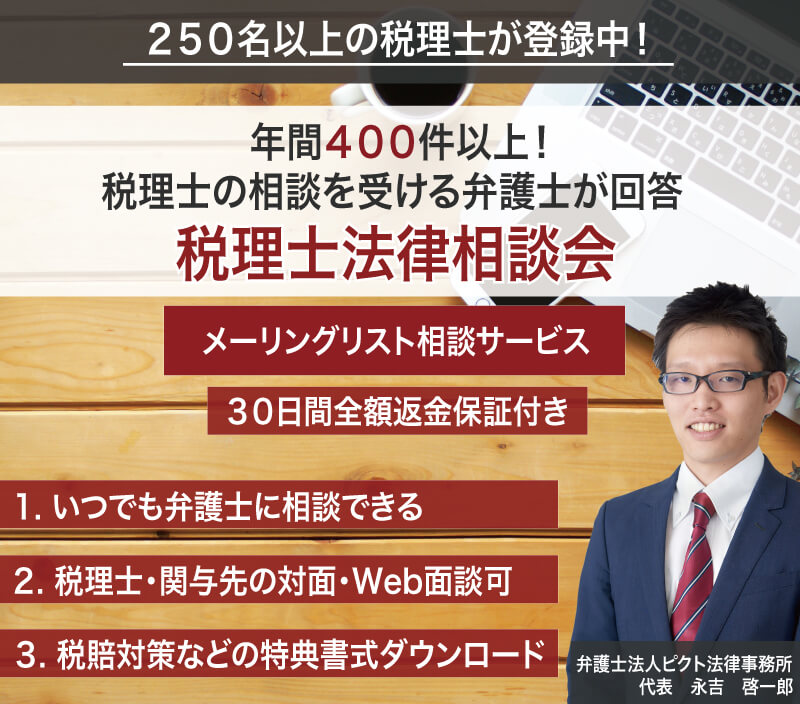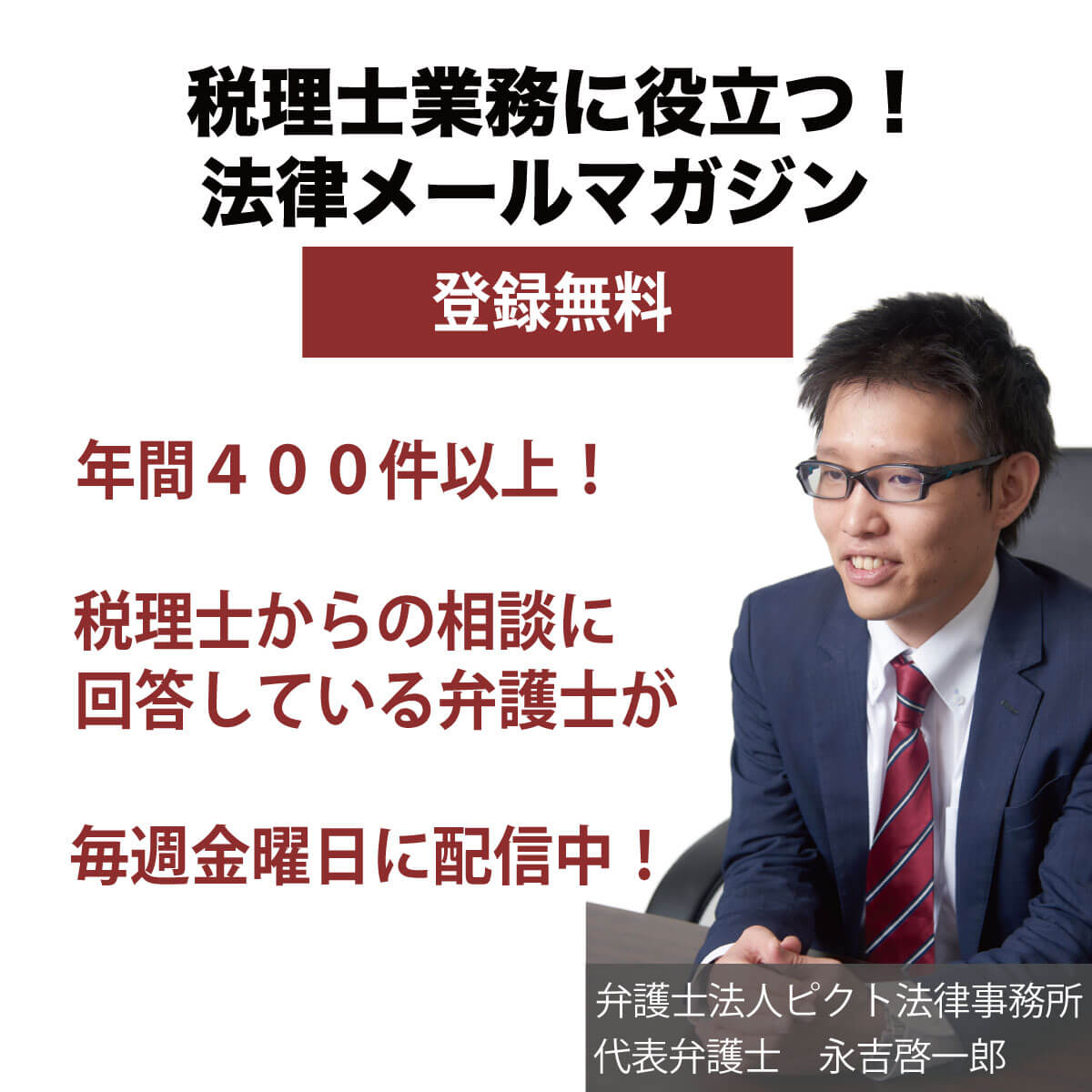贈与契約の種類(条件付贈与・死因贈与・負担付贈与)〜贈与の法務と税務②〜
前回は、贈与契約についての基本的な法務と税務の記事を書きました。贈与契約といっても、法律的には種類があります。今回は、その種類に応じた法務・税務について解説したいと思います。税理士の先生は是非、参考にしていただけると嬉しいです。
【目次】
1 単純贈与
まず、最もシンプルな形である贈与です。前回の記事はこれを前提に書いています。単純に父親の財産を息子に贈与するというだけの契約になります。課税関係も前回の通りになります。
<参考>
贈与契約とは!?〜贈与の法務と税務①〜
2 条件・期限付贈与
次に、条件・期限付贈与というものが存在します。これは、贈与の効力が、どういう場合に発生するかを定めることができる類型です。
2.1 条件・期限付贈与の法務
これはつまり、贈与によって財産が移転するために条件や期限を付けるものです。条件と期限の詳細については、別の記事で書きますが、例えば下記のようなものが「条件付贈与契約」です。
| 贈与者 | 祖父 |
|---|---|
| 受贈者 | 孫 |
| 贈与財産 | 1,000万円の金銭 |
| 条件 | 孫の税理士試験の合格 |
というような形で、ある一定の条件(将来発生するか未確定のもの)が成立した場合に、贈与の法的効果(財産の移転)を発生させるというものです。この例でいうと、「孫の税理士試験の合格」という条件が成立しなければ、贈与の効果が発生しません。
なお、「期限」付贈与契約は、「条件」とは異なり、将来発生が確実なことを契機として、贈与の効果が発生するものです。例えば、「孫が20歳になった時」等です。
実務的に、このような贈与をするべきか否かは、まさに依頼者さまのご要望等でケースバイケースではあります。例えば、上記の例でいうと、「祖父」が今はまだちゃんとしているが、「孫」が税理士試験に合格する頃には、痴呆等になり「意思能力」を欠いて、有効な契約が結べない可能性もあると思います。今のうちに条件付き贈与契約を締結しておけば、条件が成立した時に問題なく「孫」は、贈与財産を得ることができます。意思能力は、契約成立時に必要であって、条件成立時に必要なわけではないからです。
2.2 条件・期限付贈与の税務
課税物件等については、単純贈与と相違ありません。ただし、課税時期については、条件が成立して、初めて贈与の効果が生じるわけですから、条件の成立時ということになります。
3 死因贈与
次に死因贈与です。死因贈与は、贈与者の死亡という事実が生じた場合に、贈与の効果が発生するというものです。つまりは、「2」のうち期限付き贈与ということになります。にもかかわらず、特別に取り上げたのは、法務的にも、税務的にも他とは違う効果が生じるからです。
3.1 死因贈与の法務
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
死因贈与の場合、この条文の通り、「この性質に反しない限り」遺贈に関する規定が準用されるとされています。遺贈と死因贈与の異同の主なものは下記の表の通りです。違う部分が、「この性質に反する」部分になるということです。
| 種類 | 法的性質 | 能力 | 代理 | 方式 | 遺留分減殺請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺贈 | 単独行為→受贈者の承諾不要 | 15歳(民法961条)→15歳以上の者がした遺贈は、制限行為能力者を理由とする取消不可 | 不可 | 厳格に決定(民法967条~) | 可(民法1031条) |
| 死因贈与 | 契約→受贈者の承諾必要 | 20歳(民法3、4条) | 可 | 遺贈の条文は準用されない | 可(民法554条、1031条) |
主にあくまでも死因贈与は契約である一方、遺贈は単独行為であるという点から生じる違いです。死因贈与には、手続き上も遺言のように方式(公正証書遺言等の作成)の縛りはありません。
契約である以上、法律的には、口頭であっても成立するものです。ただし、死因贈与は、贈与契約の成立と死亡により発生する約束があったことを立証しなければならないので、契約書は必ず作った方が良いのは間違いありません。
3.2 死因贈与の税務
死因贈与の遺贈に近い性質から、税務上も他の贈与とは当然ですが違いが生じます。受贈者が個人か法人かで、課税関係が変わります。
なお、死因贈与の場合は、上記の通り、口頭でも成立しますが、課税実務上、契約書等なしで、その存在を課税庁に認めさせるのは著しく困難です。必ず、契約書を作成しましょう。
① 受贈者が個人の場合
相続により財産を取得したものとして、相続税の課税対象になります(相続税法1条の3第1号括弧書)。
② 受贈者が法人の場合
受贈者である法人に対しては、法人税課税(法人税法22条2項)がされ、贈与者には、みなし譲渡所得課税(所得税法59条1項1号)が課されることになります。
不動産取得税
もう1点注意が必要なのが、死因贈与対象財産が不動産の場合です。
相続または遺贈による取得は非課税規定(地方税法73条の7第1号)があり、非課税とされています。
しかし、死因贈与については、この非課税規定はありません。死因贈与の性質から、非課税規定を適用しても良さそうなものの、裁判所はこの規定はあくまでも形式を求めます。ですので、死因贈与の場合には、贈与を原因とする財産の取得として、不動産取得税が課税されます(仙台高裁平成2年12月25日判決)
4 負担付贈与
負担付贈与とは、贈与契約の内容の一部として、贈与する代わりに相手に一定の作為・不作為を求めるものです。
4.1 負担付贈与の法務
条件付贈与と似ていますが、条件付贈与は贈与の効力(財産の移転)の発生をするかしないかの問題です。一方で、負担付贈与は、贈与の効力(財産の移転)自体は発生させつつ、受贈者に一定の義務を課すというものになります。
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与は、あくまでも贈与財産の対価として義務を負うものではない(売買との違い)ですが、実態として、その区別は曖昧です。そこで、負担付贈与には、このような条文で売買等にも適用される規定を準用しています。
4.2 負担付贈与の税務
負担付贈与の課税については、昔から租税回避の温床となるとして、いろいろと通達等でも対策がなされてきたようですが、統一的な解決がされているかというと微妙なところです。
贈与者または第三者が利益を得るケース
負担付贈与の場合、受贈者がその負担を果たすことによって、贈与者または第三者が利益を得ることになる場合には、その利益について、課税関係が生じます。全てのパターンを書くと前回の記事や上記との重複も多くなるので、違うケースを説明します。
個人間の贈与の場合、通常の贈与の場合、所得税法59条1項1号のみなし譲渡所得課税の適用はなく、贈与者には課税関係は生じません。しかし、負担付贈与の場合には、贈与者が利益を得る以上、負担を対価とする譲渡所得課税が生じることになります(最高裁昭和63年7月19日)。
負担付贈与の場合には、第三者のための行為というケースもままあります。第三者が個人であれば、その第三者は利益相当額の贈与を受けたとして、贈与税の対象にもなるでしょう。
5 まとめ
以上が、各贈与契約の種類によっての法務税務の注意点になります。贈与は何かと課税関係が複雑になりやすいところでもありますので、是非ご参考になさっていただきたいです。
次回は、贈与契約の成立はあったが、その後、取消しや解除された場合等の税務を中心とした記事を書きたいと思いますので、是非ご覧ください。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日