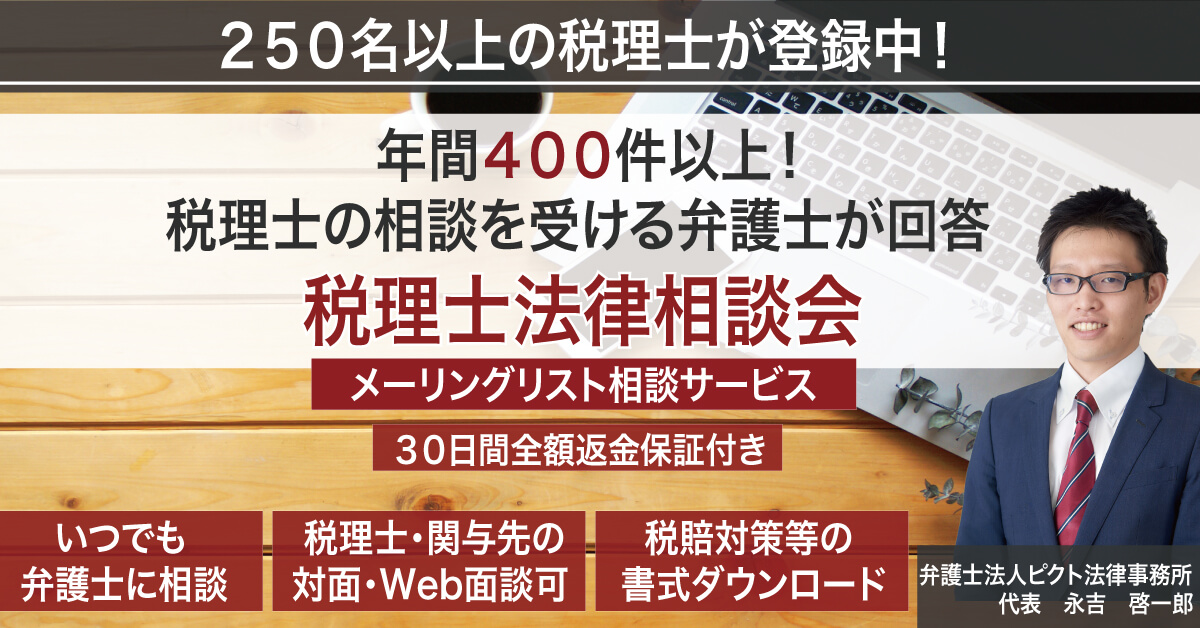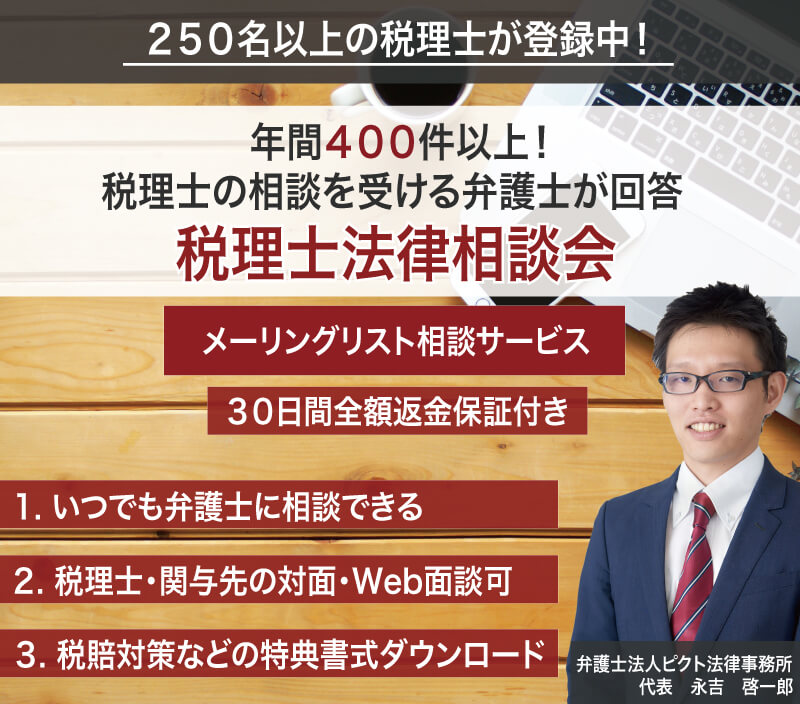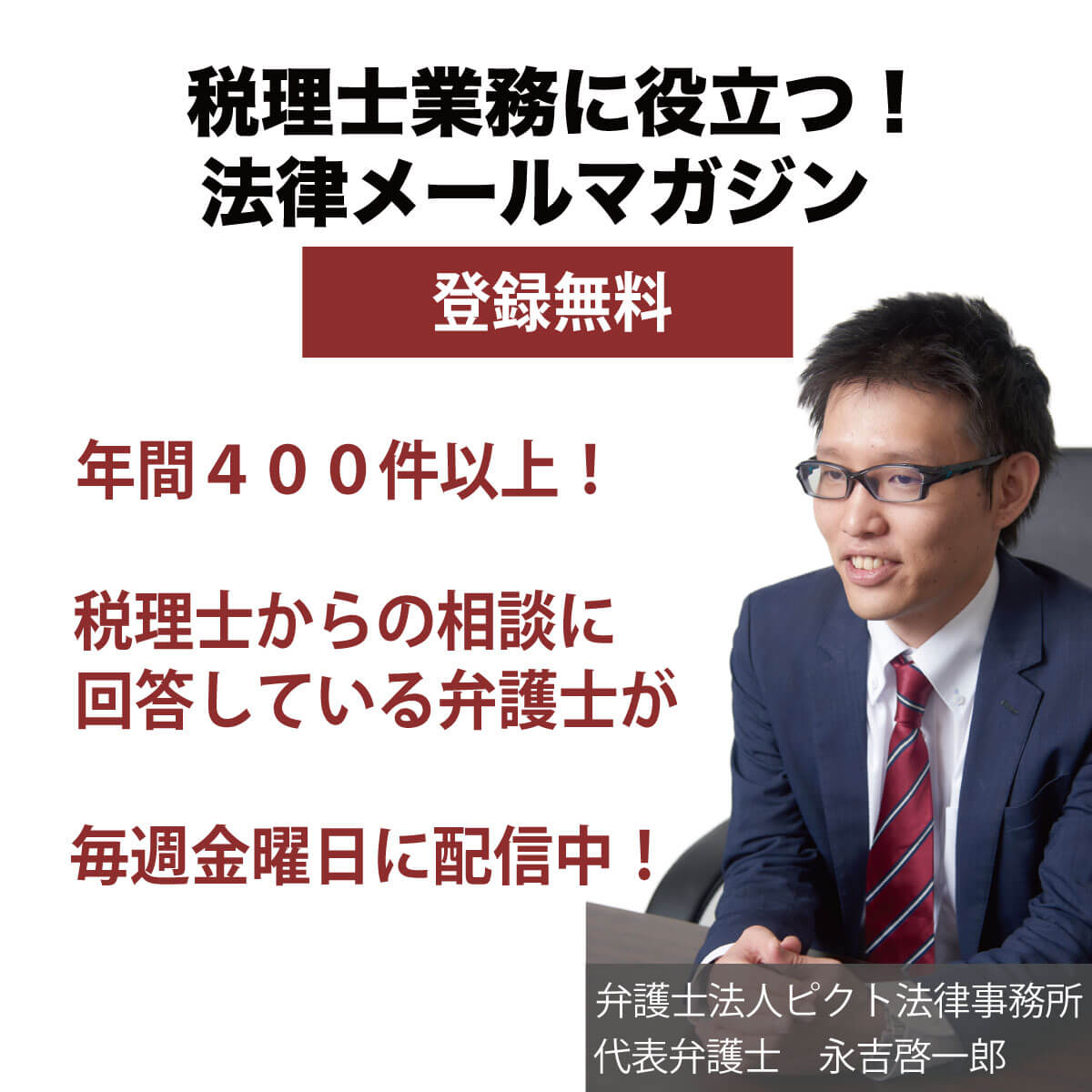従業員の不正(横領等)に対する損害賠償請求権の益金算入時期と貸倒れ〜貸倒れの税務と法務⑦
この貸倒損失シリーズも7つ目になりました。今回は、従業員の不正が発覚し、損害賠償請求権が生じた場合の問題について解説したいと思います。単に貸倒れの問題だけではなく、従業員の不正の場合の税務上の処理を含めて、税理士の先生からよくご質問いただくところですので、そのあたりを中心に解説したいと思います。
【目次】
1(元)従業員への損害賠償請求権の益金算入時期
まず、従業員が会社に損害を与えた場合、その損害については、損害が生じた事業年度(不正があった時)の損失として、損金となります(法人税法22条3項3号)。それでは、それに伴い生じた損害賠償請求権の扱いはどうなるのか見ていきましょう。
1.1 損害賠償請求権の益金算入時期の考え方
不正があった場合、会社から従業員に対して、損害賠償請求権が発生することになるわけですが、ざっくりいうと、この損害賠償請求権を損失が生じた事業年度の益金となる(同時両建説)のか、それとも裁判や当事者の示談等の結果がでた事業年度の益金とすべき(異時両建説)かについては、考え方が分かれる部分であるのは、税理士の先生がご存知の通りです。
前者(同時両建説)は、損害が生じた時点から損害賠償請求権は発生しているという民事法上の考え方を重視したもので、後者(異時両建説)は、そうは言っても損失額の「確定」という観点からは、争いなく具体的に金額が確定しなければ、実際の益金額がいくらかはわからないよね!という考え方を重視したものです。
実務上は、このように明確にどちらの説に立つという風には動いていないのですが、考え方の前提をここでは説明させていただきました。
1.2 従業員の横領等の金銭の詐取や使い込みがあった場合の判例の考え方
このような考え方に争いがあることは良いとして、従業員の横領等の金銭の詐取や使い込みがあった場合に、実務上どのように考えていくのか、ということについては、最高裁平成21年7月10日決定が道筋を立てる基準になるかと思います。この決定(厳密には、東京高裁平成21年2月18日判決を認めたもの)は、民事上の原則に則りつつ、例外を一切認めないわけではないというバランスをとったものかと思います。
-
東京高裁平成21年2月18日判決(【】と下線:筆者)
-
本件のような【従業員が架空外注費を計上して会社の金員を詐取した事例】不法行為による損害賠償請求権については,通常,損失が発生した時には損害賠償請求権も発生,確定しているから,これらを同時に損金と益金とに計上するのが原則であると考えられる(不法行為による損失の発生と損害賠償請求権の発生,確定はいわば表裏の関係にあるといえるのである。)。
もっとも,本件のような不法行為による損害賠償請求権については,例えば加害者を知ることが困難であるとか,権利内容を把握することが困難なため,直ちには権利行使(権利の実現)を期待することができないような場合があり得るところである。このような場合には,権利(損害賠償請求権)が法的には発生しているといえるが,未だ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとはいえないといえるから,当該事業年度の益金に計上すべきであるとはいえないというべきである。
つまり、原則として、同時両建説のように民事上の考え方を重視し、損失と同時に損害賠償請求権を益金計上し、例外として、直ちには権利行使(権利の実現)を期待することができないと評価できる場合であれば、同時ではないこともあり得るとしたわけです。
ただし、従業員の金銭の詐取や使い込みの事案では、この例外的な場合にあたるというはかなり特殊なケースであると考えた方が良さそうです。
なぜならば、自社の金銭について、自社の従業員が行っていることですので、相当巧妙にされたものでなければ、決算期などにおいて、会計資料として保管されている請求書や振込み依頼書をチェックすれば、見つけることができたでしょ!?といわれてしまうケースがほとんどだからです。
1.3 通達(法人税法基本通達2−1ー43)との関係
-
法人税基本通達2−1−43(下線:筆者)
-
(損害賠償金等の帰属の時期)
2-1-43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)
(注) ・・・省略・・・
上記の判例を見て、「あれ!?」と思われた税理士の先生もいらっしゃるかもしれません。その通りで、この通達によると損害賠償金は、実際に支払いを受けた日等に益金にすればよく異時両建説の考え方を前提にしているのでは?という点です。
この通達の改正の経緯等と裁判例との関係も見ていくといろいろと長い話になるのですが、ここでは、従業員の不正事例についてはこの通達による損金算入ができるというわけではない点について解説します。
もうお分かりかと思いますが、上記通達は、下線部分で「他の者から」とされています。役員や従業員の不正の場合は、この「他の者」ではないので、この通達の適用?はないとされています(あくまでも、「法人」と個人は別人格なので、「他の者」の読み方に疑義はありますが。) 。
上記の判例の中でも、
- 法人税基本通達2-1-43が,「他の者から・・・」と規定し,損失の計上時期と益金としての損害賠償金請求権の計上時期を切り離す運用を認めているのも,基本的には,第三者による不法行為等に基づく損害賠償請求権については,その行使を期待することが困難な事例が往々にしてみられることに着目した趣旨のものであると解するのが相当である。
と指摘されています。
1.4 従業員が取引先からリベートを受けていた場合
上記では、会社の金員を従業員が詐取したり、使い込みがあったりという事例を前提にしておりますが、実務上、従業員が取引先等からリベートを受けたという事例の場合には、別に考えなければならない問題があります。
このような事例の場合、そもそもそのリベートが法人に収益として帰属するのか、つまりは、これは従業員が個人としての取引先等とした契約に基づいているとも考えられ、個人にそもそも帰属するものではないのかという点が問題になりますので注意が必要です。
ここでは、詳細には触れませんが、法人税法11条、消費税法13条の実質所得者課税の原則から、従業員が単なる名義人にすぎないといえ、法人がリベートの法律上の受領者と評価できるかの事実認定の問題になります。
この問題については、有名な裁判例としては、仙台地裁24年2月29日判決があります。この裁判例は、
◯就業規則上もリベートの受領が禁止されていたこと
◯従業員自身の判断で、受領したリベートを費消していたこと
等の事実から、従業員が単なる名義人とはいえず、個人としての法的地位に基づいてリベートを受け取っていたと評価し、法人には収益がそもそも帰属しないとしています。
2 損害賠償請求権の貸倒損失計上時期
上記の「1.4」で、そもそもリベートの収益が会社に帰属しない場合は別として、従業員の金員の詐取や使い込みにより損失が生じた場合には、原則として、損失が生じた事業年度(不正行為があった事業年度)に、損害賠償請求権が益金となります。
そうすると、実際に損害賠償請求権を益金に計上したとしても、それが回収できない場合には、その損害賠償請求権という債権については、別途貸倒れの要件事実が充足された時点で、貸倒損失として計上するということになります。
3 まとめ
今回は、貸倒れというよりも、従業員が不正行為を行った場合の損害賠償請求権についての税務処理についての解説が中心となりました。ただし、貸倒れの判断をするにあたっては、まずは対象債権に関することを明確に把握する必要があると考えられますので、このシリーズで触れさせていただきました。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日