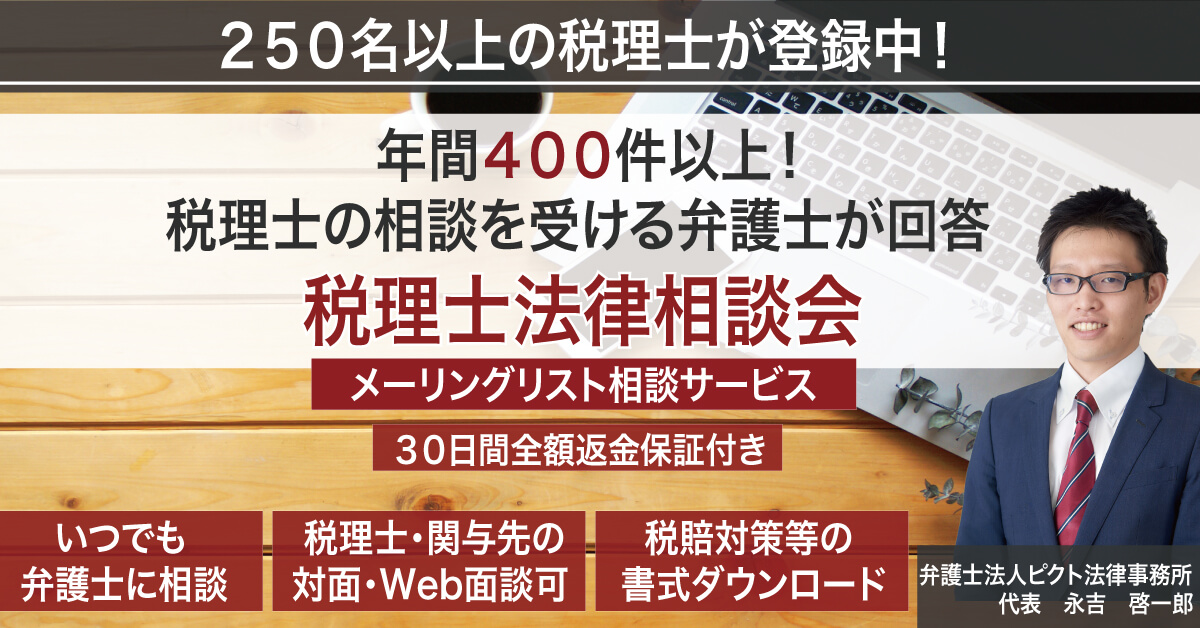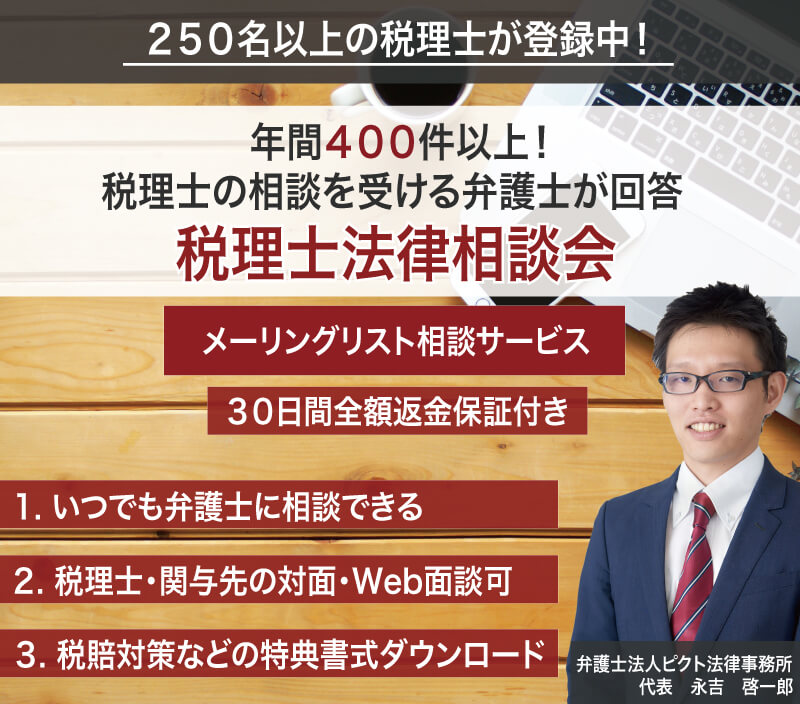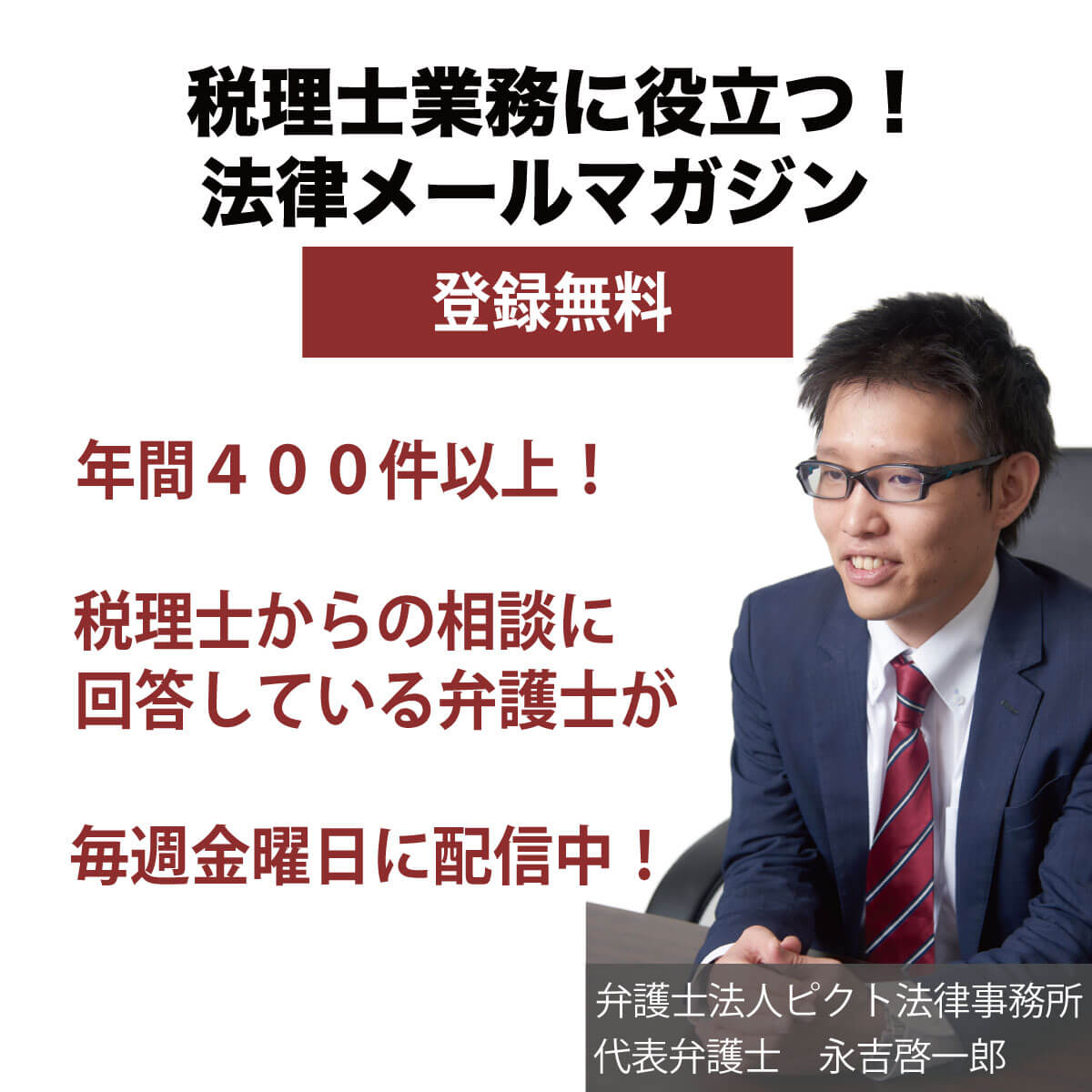貸倒損失と法務の総論 〜貸倒れの税務と法務①〜
今回からしばらくシリーズものとして、「貸倒損失」をテーマに記事を書きたいと思います。この貸倒損失ですが、債権の成立・消滅等が争点になるケースも多いので、実は貸倒損失の判断には、法務判断が深く関わってきます。
まずは、シリーズの第1弾として、今回は貸倒損失等についての総論的な部分から書いていきたいと思います。
【目次】
1 貸倒損失とは!?
税理士の先生にお話すること自体、おこがましさを感じますが、シリーズ第1回ですので、まずここから説明したいと思います。
1.1 貸倒れは固有概念?
「貸倒れ」とは、回収不能な金銭債権の状態をいいます。この「貸倒れ」ですが、これは法律の中では、税法上の固有概念になります。
参考:固有概念と借用概念について
ですので、民事上の法律の中には、「貸倒れ」というものはなく、法務的にいうと単純に債権回収の失敗を意味する言葉になります。
1.2 関連する税目
| 税目 | 関連規定 |
|---|---|
| 法人税 | 法人税法22条3項3号,4項 法人税法基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3,9-4-1,9-4-2 |
| 所得税 | 所得税法51条2項 所得税基本通達51-10〜17 |
| 消費税 | 消費税法39条 消費税法施行令59条,消費税法施行規則18条 |
| 相続税 | 相続財産の有無及び財産評価 財産評価基本通達204,205 |
簡単に関連する税目をあげるとこのようになるかと思います。
なお、相続税の場合は、法律上相続前に消滅していれば相続財産になりませんし、そうでないケースでは財産評価の問題になるかと思います。
この記事では、貸倒れの議論されるときに扱われることが多い「法人税」を題材にしていきたいと思います。
1.3 貸倒損失の課税要件事実と計上時期
貸倒損失の根拠は、法人税法22条3項3号の「当該事業年度の損失」にあたるため損金とできるというのが判例の立場です。
そして、この「損失」については、損失が実現している必要がある(実現主義)ということから、結局のところ、課税要件事実として、金銭債権が社会通念上回収が不可能と評価できる事実であり、回収不能となった事業年度において、損金になると考えられます。
2 実務上の基準となる通達の存在
法人税法から考えて理論的にいうと、上記の課税要件事実が貸倒れ損失の要件となると思いますが、「社会通念上回収が不可能」と評価できる場合はどういう場合なのか?という点があまりにも曖昧です。なので、実務上、この「回収が不可能」と評価される場合の基準としては、税理士の先生がご存知の通り、「法人税法基本通達9−6−1〜3」というものが存在します。以下、簡単にこの通達をご紹介します。この通達は実務上は大きな意味を持っていますが、通達はあくまでも納税者を拘束する法的拘束力があるわけではないのは、このサイトで繰り返し申し上げている通りです(通達の法的な説明についてはこちら記事)。
| 区分 | 債権の種類 | 処理/取扱い | 損失金額 | 損失金額 |
|---|---|---|---|---|
| 法律上の貸倒れ | 金銭債権 | 損金処理 | 法的に切捨てられることとなった部分の金額 書面により明らかにされた債務免除額 |
法的手続き等により債権の切捨ての事実が発生した日の属する事業年度 |
| 事実上の貸倒れ | 金銭債権 | 損金経理? | 金銭債権の全額 ※担保物があるときは、その処分により受け入れた金額を控除した残額 |
金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった事業年度 ※担保物があるときはその処分後 |
| 形式上の貸倒れ | 金銭債権のうち売掛債権等 ※売掛金、未収請負金、その他これらに準ずる債権 ※貸付金その他これらに準ずる債権を含まない |
損金処理? | 売掛債権の額から備忘価額を控除した残額 | 債務者との取引停止以後1年以上経過した日等 |
この表が、「法人税法基本通達9−6−1〜3」のうち、「回収が不可能」と評価できる事由を除いたものになります。この事由についてが一番大切なので、以下一つずつ紹介します。
なお、処理/取扱いの欄の損金経理に「?」をつけたのは、通達の解説書等では「損金経理」が必要だとされている例が多いのですが、通達上「できる」とされているのみですし、法人税法上の「回収が不可能」の要件についての基準を定めているに過ぎない以上、損金経理を要件とすれば、通達による要件の付加であり、租税法律主義の観点から問題があると思われるからです(通達課税についての記事)。
2.1 法律上の貸倒れ
| 事由 |
|---|
| 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定 |
| 特別清算に係る協定の認可の決定 |
| 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの |
| 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、内容が合理的な基準によるもの |
| 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合の書面による債務免除 |
通達上の「法律上の貸倒れ」に該当するものになります。ここに含まれていない事項でも、債権が消滅して、貸倒れになるものはあります。例えば、消滅時効等もそうです。また、実務上はどの事由にあたるのかの判断が難しいものも多いです。その他の事項も含めて、今後連載の中で解説していきますので、今回は紹介に留めます。
2.2 事実上の貸倒れ
| 事由 |
|---|
| 金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合 |
法的には権利が消滅していないが、回収ができないという場合です。「貸倒れ」という表現には一番しっくりくるケースです。ただ、実務上は、計上時期の関係や対税務署が納得しやすいように、このようなケースでも、法律上の貸倒れのうちの「債務免除」(債権放棄)をする税理士の先生が多いと思います。
通達上の事実上の貸倒れは、「全額」回収できないことが明らかな場合ということになっている点も、ご承知の通りかと思います。
これは、これまでの判例の判断を前提としたものです。有名なものでいうと興銀事件等もそのように言っています。判例の位置付けを通達の区分に分けるのは実は難しいのですが、以下のものです。
なお、この判例が有名になっているのは、この回収不能の判断は、債務者側の事情のみならず、「債権者側の事情」も考慮するよと言った点にあります。
2.3 形式上の貸倒れ
| 事由 |
|---|
| 継続的取引先である債務者の資産状況や支払能力に問題が発生し、取引停止(※)以後1年以上経過した場合※取引停止、最後の弁済期限、最後の弁済日のうち最も遅い日 |
| 同一地域の債務者の売掛債権の総額が、取立のために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対して支払い督促をしたにもかかわらず弁済がないとき |
| ※商品販売や役務の提供等の営業活動によって発生した売掛金、未収加工料、未収請負金、広告代理等の未収手数料、倉庫業者の未収保管料、不動産業者の未収地代・家賃に限られており、貸付金やその他貸付金に準ずる債権は含まない。 ※売掛債権について担保物がある場合は、この規定は適用できない。 |
この規定は、売掛債権等について、現行(平成29年5月10日現在)の民法には、短期消滅時効というものがあり、詳しくはこのシリーズの中で書きますが、2年などで債権が消滅するものがあるため、他の債権よりも緩やかな通達基準がおかれていると考えられます。民法改正後に、この短期消滅時効が排除され、原則5年に変更になるので、民法改正がこの通達にどのように影響をするのかは注視しておいた方が良いでしょう。
3 貸倒損失の証明責任
次に上記の貸倒れの課税要件事実の証明は誰がしなければならないかという点ですが、貸倒れについても、「法律上」は、課税庁が負うことになります。課税要件事実の証明責任についてはこちらの記事をご覧ください。
ただし、何やら小難し話なのですが、裁判例は、法律的な証明責任は課税庁が負うものの、納税者側で、
- ①貸倒損失の対象となる債権の
- ◯発生原因
- ◯内容
- ◯帰属
- ◯回収不能の事実について、
具体的に特定して主張して、
②貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させる立証
がなされなければ、事実上、貸倒れの要件事実は不存在と推定されるとしています。
これは、現実論として不存在の立証を課税庁がするのは著しく困難なことや、債権は原則として回収できるものであることから、例外的な回収不能という事情については、ある程度納税者側にも責任を負ってもらわないといけないという発想からこのように判断されています。
もちろん、「ある程度合理的に」という程度ですので、証明責任を果たしたというレベルまで立証しなければならないというわけではないのですが、何も証拠がない状態では納税者側は負けてしまうということです。
つまり、「◯発生原因◯内容◯帰属」という点については契約書を作成しておき、「回収不能の事実」については、先方の財務諸表や内容証明郵便等の回収努力をした証拠を残しておくことが重要ということになります。
とはいっても、「回収不能の事実」の証拠を残すのは技術的に専門性が必要なケースも多いので、それはこのシリーズの中で解説していきます
4 まとめ
以上、長くなりましたが、貸倒損失の総論的な話になります。 この他にも寄附金との関係等もありますが、そのあたりもシリーズの中で触れていきますので、ぜひ、ご参考にしていただければ嬉しいです。
- 税賠を防ぐ!税務(税理士)顧問契約書のポイント - 2022年8月28日
- 取得財産を超える遺産分割における代償金と贈与税など - 2022年7月28日
- 特定財産承継(相続させる旨の)遺言と異なる遺産分割と贈与税など - 2022年7月27日
- 遺産分割をやり直すと贈与税などが課税されるのは本当か? - 2022年7月26日
- 税理士が損害賠償請求を受けた場合の対応方法 - 2022年7月12日